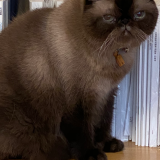ログインして質問する
租税法過去問参考答案例令和元年第1問設問1についての質問となります。
答案例では、法法22条2項から、A社の益金算入額を4000万円と導いています。しかし、22条の2が新設されていることから、以下の通り、22条の2第4項を適用して論述するべきではないでしょうか。
益金の額は、譲渡をした資産の引渡しの時における価額(22条の2第4項)→引渡し時の価額は、第三者間で通常付される価額(時価)4000万円
参考リンク
参考リンク
お世話になっております。ご質問を有難うございます。以下、ご回答をさせて頂きます。
令和元年の出題趣旨では、「設問1は,法人による資産の低額譲渡について,益金の側の法人税の取扱いにつき問うものである。解答に当たっては,まず,益金の額への算入の規定である法人税法第22条第2項を指摘し,同項が益金の額に算入すべき金額に「無償による資産の譲渡」が含まれる旨を規定していることとその趣旨ないしは理由について述べることが必要である。その上で,低額による資産の譲渡が「無償による資産の譲渡」と「有償による資産の譲渡」のいずれに該当するかにつき述べ,低額による資産の譲渡の場合に資産の時価まで益金に算入される旨とその理由を述べることが期待されている。」とございます。
上記の趣旨にしたがって「無償による資産の譲渡」の解釈に焦点をあてて、解答例を作成しております。
以上になります。宜しくお願い致します。 (さらに読む)
令和元年の出題趣旨では、「設問1は,法人による資産の低額譲渡について,益金の側の法人税の取扱いにつき問うものである。解答に当たっては,まず,益金の額への算入の規定である法人税法第22条第2項を指摘し,同項が益金の額に算入すべき金額に「無償による資産の譲渡」が含まれる旨を規定していることとその趣旨ないしは理由について述べることが必要である。その上で,低額による資産の譲渡が「無償による資産の譲渡」と「有償による資産の譲渡」のいずれに該当するかにつき述べ,低額による資産の譲渡の場合に資産の時価まで益金に算入される旨とその理由を述べることが期待されている。」とございます。
上記の趣旨にしたがって「無償による資産の譲渡」の解釈に焦点をあてて、解答例を作成しております。
以上になります。宜しくお願い致します。 (さらに読む)
法律実務基礎科目がまだ手付かずです。お世話になっている中村充先生の講座は近々配信されますでしょうか。されないとすれば、初学者としてこれからどのように勉強を進めていけば良いでしょうか。テキスト、中村先生おすすめの講座があればご紹介いただけるでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
申し訳ありません、現段階では中村講師による配信予定はありません。
実務基礎については、西口先生・新庄先生の『法律実務基礎完璧講義』のご受講をご検討くだされば幸いです。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
申し訳ありません、現段階では中村講師による配信予定はありません。
実務基礎については、西口先生・新庄先生の『法律実務基礎完璧講義』のご受講をご検討くだされば幸いです。 (さらに読む)
刑法の短答の勉強方法について質問です。
今年の刑法短答では穴埋め問題が多数出題されました。この形式の問題に慣れるために旧司の短答過去問にも取り組んだほうが良いのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
穴埋め問題は新司法試験になってからも今年に限らず出題されていますので、まずは新司法試験の過去問を優先して解くようにしてください。
どちらかというと、時間切れになった受験生が多いと思いますので、日頃の学習では制限時間を設けて問題検討をする習慣をつけていきましょう。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
穴埋め問題は新司法試験になってからも今年に限らず出題されていますので、まずは新司法試験の過去問を優先して解くようにしてください。
どちらかというと、時間切れになった受験生が多いと思いますので、日頃の学習では制限時間を設けて問題検討をする習慣をつけていきましょう。 (さらに読む)
[刑法]共犯者間における抽象的事実の錯誤について質問です。
かかる論点は、どの要件充足性を判断する上で問題となる論点なのでしょうか?
共謀(=特定の犯罪についての意思連絡)が認められるか。という問題なのでしょうか?
だとすれば、共同正犯の要件たる②共謀に基づく実行行為を認定する前に書くこととなってしまい、錯誤であることを述べづらいので困っています。
答案を実際に書く際の視点からご教授願います。
刑法では、体系上の位置づけを常に意識する必要がありますから、大変いいご質問だと思います。
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。 (さらに読む)
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。 (さらに読む)
刑法の正当防衛における、「防衛行為が第三者に対して行われてしまった場合」について質問です。
かかる論点は、どの要件との関係で問題になるのでしょうか?
(正当防衛における)「不正」性(=自己が防衛行為を行なった者についての「不正」性)が認められない。という理解で良いでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
いわゆる「防衛行為と第三者」の論点については、①侵害行為者が第三者の物を利用した場合、②防衛行為者が第三者の物を利用した場合、③防衛行為の結果、第三者に対する法益を侵害する場合が挙げられます。そして、これらの論点は、防衛行為者の行為について違法性阻却事由を検討する(「第三者」を被害者とする犯罪が成立するか)際に問題となります。
要件レベルとしては、「急迫不正の侵害」の要件が問題となります(第三者本人が侵害行為に及ぶことは考えにくいため、①のケースでなければ基本的には急迫不正の侵害を否定されることが一般的な理解だと思います)。
この論点は最高裁判例があるわけでもないですし、淡々と正当防衛の要件に当てはめていけば問題ありません。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
いわゆる「防衛行為と第三者」の論点については、①侵害行為者が第三者の物を利用した場合、②防衛行為者が第三者の物を利用した場合、③防衛行為の結果、第三者に対する法益を侵害する場合が挙げられます。そして、これらの論点は、防衛行為者の行為について違法性阻却事由を検討する(「第三者」を被害者とする犯罪が成立するか)際に問題となります。
要件レベルとしては、「急迫不正の侵害」の要件が問題となります(第三者本人が侵害行為に及ぶことは考えにくいため、①のケースでなければ基本的には急迫不正の侵害を否定されることが一般的な理解だと思います)。
この論点は最高裁判例があるわけでもないですし、淡々と正当防衛の要件に当てはめていけば問題ありません。 (さらに読む)
未回答の質問
お世話になっております。令和4年度民法設問2について質問です。取得時効が認めれるかにおいて、185条「新たな権原」の検討前に187条1項「承継人」に該当するかを論じる必要はないのでしょうか。
参考リンク
参考リンク
いつもお世話になっております。
勉強の進め方について質問です。
現在は1科目を集中して講義インプット→短答過去問解く→講義も過去問も1周終了したら次の科目の勉強に入っていたのですが、1科目の量が多すぎて記憶が定着せず効率が良くないなと感じてます。2ヶ月でやっと1科目1周できた程度しか進めませんでした。
参考までに、諸先生方の学習方法をご紹介いただませんでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
インプット講義については「理解しているか」に重きを置いていました。そして、1回勉強して試験日まで覚え続けることは不可能なので、とにかく最後までインプットを1周することを心掛けていました(「定着しているか」については論文対策で答案構成や答案が書けるかどうかで確認していました)。
インプット講義で学習する知識をすべて覚えたからといって合格できるわけではありませんし、インプット講義で扱う細かい知識まで覚えていなくても合格できます。あくまでもインプット講義で学ぶことは下地となるものなので、講義内容をまずは「理解すること」に努めてください(定着させようと思っても定着しません。合格レベルに達する頃にはインプット講義が知らず知らずのうちに定着していた、という感じになっています)。
「覚えているか」を確認するのは試験日の1か月前にやるべきことです。短期合格できる人はほんの一握りなので愚直に知識の刷り込みを行いましょう。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
インプット講義については「理解しているか」に重きを置いていました。そして、1回勉強して試験日まで覚え続けることは不可能なので、とにかく最後までインプットを1周することを心掛けていました(「定着しているか」については論文対策で答案構成や答案が書けるかどうかで確認していました)。
インプット講義で学習する知識をすべて覚えたからといって合格できるわけではありませんし、インプット講義で扱う細かい知識まで覚えていなくても合格できます。あくまでもインプット講義で学ぶことは下地となるものなので、講義内容をまずは「理解すること」に努めてください(定着させようと思っても定着しません。合格レベルに達する頃にはインプット講義が知らず知らずのうちに定着していた、という感じになっています)。
「覚えているか」を確認するのは試験日の1か月前にやるべきことです。短期合格できる人はほんの一握りなので愚直に知識の刷り込みを行いましょう。 (さらに読む)
民訴法の管轄について質問です。
4S基礎講座で5条12号の「不動産に関する訴え」は不動産売買代金支払請求訴訟は当てはまらず、不動産所在地に限らなくて良いと解説してくださってたのですが、この訴えは5条1号の「財産権上の訴え」にあたり管轄は義務履行地になり、不動産所在地ではできない、と理解して良いのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
この場合は金銭支払請求ですので、管轄は義務履行地(5条1号)になると考えられます。
不動産に関する訴えには当たりませんが、合意管轄で定めれば不動産所在地で裁判することも可能です。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
この場合は金銭支払請求ですので、管轄は義務履行地(5条1号)になると考えられます。
不動産に関する訴えには当たりませんが、合意管轄で定めれば不動産所在地で裁判することも可能です。 (さらに読む)
未回答の質問
これだけ!75の刑法の第7回で述べられていた2項強盗についてです。
財産的利益の移転の確実性・具体性が認められない場合、「暴行・脅迫」の要件が切れ、2項強盗の未遂も成立しない。との説明がありましたが、これは、実行の着手が認められない=不能犯となる。との理解でよいのでしょうか?
また、その場合、単なる暴行・脅迫(傷害、殺人)罪となるという帰結でしょうか?
所得税法テキストp16の記載について、利子所得と配当所得についてまとめてありますが、全体的に記載内容に違和感があります(e.g.利子所得の定義に配当所得にあたる内容が含まれているなど)。
スタンダード所得税法も参照しましたが、同様の主旨の記述は見当たりませんでした。
誤字・脱字というレベルではないので、おそらく何らかの文献等からコピペorまとめたものと思いますが、出典を教えてください。
参考リンク
参考リンク
御質問を頂き、有難うございます。以下、お答えをさせて頂きます。
ご指摘の点について、確認いたしました。
当該文章は、イメージをしやすいように、分かりやすくまとめたものになります。特定の文献からではなく、条文(所得税法第23条・第24条)を基に理解を補助するために作成しました。
ご指摘の「利子所得に配当所得にあたる内容が含まれている」とのご指摘については、文章の表現上、両者の区別が明確でなかったために生じたものと考えております。
正確には、利子所得と配当所得は所得税法上別の区分で定義されており、条文に従うと以下の通りです。
利子所得(所得税法第23条):預貯金の利子、公社債の利子等、金融資産の貸付け等から生じる利息収入
配当所得(所得税法第24条):株式や出資金に対する利益の配当・剰余金分配等
したがいまして、元の文章はあくまでイメージを持ちやすくして頂くための理解補助のまとめであり、法的定義に完全に沿ったものではございません。
誤解を与えてしまい、申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
ご指摘の点について、確認いたしました。
当該文章は、イメージをしやすいように、分かりやすくまとめたものになります。特定の文献からではなく、条文(所得税法第23条・第24条)を基に理解を補助するために作成しました。
ご指摘の「利子所得に配当所得にあたる内容が含まれている」とのご指摘については、文章の表現上、両者の区別が明確でなかったために生じたものと考えております。
正確には、利子所得と配当所得は所得税法上別の区分で定義されており、条文に従うと以下の通りです。
利子所得(所得税法第23条):預貯金の利子、公社債の利子等、金融資産の貸付け等から生じる利息収入
配当所得(所得税法第24条):株式や出資金に対する利益の配当・剰余金分配等
したがいまして、元の文章はあくまでイメージを持ちやすくして頂くための理解補助のまとめであり、法的定義に完全に沿ったものではございません。
誤解を与えてしまい、申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
論パタ商法2-1-2についての質問です。Dの代理人である妻に総会が撹乱されるおそれはないと評価して、代理を認めて決議取消しの訴えはできないとしたら、間違いでしょうか。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
そのような筋も間違いではないと考えます。
妻という点をどのように評価するかによりますが、Dの意を汲んで適切にふるまうこともできると評価すれば、あげていただいた筋もあり得ると考えます。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
そのような筋も間違いではないと考えます。
妻という点をどのように評価するかによりますが、Dの意を汲んで適切にふるまうこともできると評価すれば、あげていただいた筋もあり得ると考えます。 (さらに読む)
ここ1、2ヶ月ほど短答案過去問を解いているのですが、特に憲法の肢の言い回しに引っかかり間違えることがすごく多いです。
言い回しに引っかかって、実際は正しい肢でも不正解だと感じてしまうことが多くあります。こちらで配信されている短答過去問対策講座で対策はできるでしょうか?ひたすら過去問を解いていけば慣れるものでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
過去問演習をしていく中で典型的な引っ掛けに引っかかることは減ってきます。そのため、自分の中で弱点が炙り出せるようになるまでは過去問演習を繰り返す方向で良いと思います。ただ、過去問演習はあくまでも出題されやすい範囲を絞るための短答対策の手段に過ぎません。過去問を解くことや過去問の正答率を上げることが目的とならないように気をつけましょう。
なお、BEXAの短答過去問対策講座では、頻出かつ差が付きやすい問題をピックアップしているため、消化することができれば他の受験生と差をつけられることはない(短答で足元を掬われる可能性を減らす教材としては有用)と思います。
-----
下記にて短答対策講座の一覧をご確認いただけますので、併せてご覧いただけますと幸いです。
https://bexa.jp/abouts/v/stage?ccid=156 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
過去問演習をしていく中で典型的な引っ掛けに引っかかることは減ってきます。そのため、自分の中で弱点が炙り出せるようになるまでは過去問演習を繰り返す方向で良いと思います。ただ、過去問演習はあくまでも出題されやすい範囲を絞るための短答対策の手段に過ぎません。過去問を解くことや過去問の正答率を上げることが目的とならないように気をつけましょう。
なお、BEXAの短答過去問対策講座では、頻出かつ差が付きやすい問題をピックアップしているため、消化することができれば他の受験生と差をつけられることはない(短答で足元を掬われる可能性を減らす教材としては有用)と思います。
-----
下記にて短答対策講座の一覧をご確認いただけますので、併せてご覧いただけますと幸いです。
https://bexa.jp/abouts/v/stage?ccid=156 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-13について質問です。Aの罪責については問われてませんが、回答したとして配点はあるのでしょうか。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
たしかなことはいえませんが、裁量点で配点されることはあり得ると思います。
甲乙の罪責を検討する前提としてAの罪責を検討するので、その点で裁量点の対象にはなりえると考えます。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
たしかなことはいえませんが、裁量点で配点されることはあり得ると思います。
甲乙の罪責を検討する前提としてAの罪責を検討するので、その点で裁量点の対象にはなりえると考えます。 (さらに読む)
民法の短答学習をしていて疑問が出てきました。保証人の事前求償権(民法460条)についてです。具体的には一定事由がしょうじると、保証人は、主債務者に事前に求償できると書いてありますが、仮に主債務者が求償に応じられる資力があるのなら債務を債権者に直接履行すればよく、わざわざ保証人に履行するのは回りくどいような気がするのですが、これを認めるのは何か実務的な背景があるのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民法460条において保証人の事前求償権が認められた趣旨は、同条各号に規定する事情が発生した(保証人が直ちに請求を受ける危険が切迫した)時点で、主債務者に対する求償権行使ができるようにした点にあると考えられます。 例えば、ⓐ連帯保証人の場合や、ⓑ債権者が主債務者とは連絡がつかない一方で、主債務者と保証人は連絡が取れるという場合は、主債務者ではなく保証人へ保証債務の履行を求められる場合もあり得ます。また、事前求償を認めることで、主債務者が財産散逸させる前に確実に求償権を行使できるというメリットもあります。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民法460条において保証人の事前求償権が認められた趣旨は、同条各号に規定する事情が発生した(保証人が直ちに請求を受ける危険が切迫した)時点で、主債務者に対する求償権行使ができるようにした点にあると考えられます。 例えば、ⓐ連帯保証人の場合や、ⓑ債権者が主債務者とは連絡がつかない一方で、主債務者と保証人は連絡が取れるという場合は、主債務者ではなく保証人へ保証債務の履行を求められる場合もあり得ます。また、事前求償を認めることで、主債務者が財産散逸させる前に確実に求償権を行使できるというメリットもあります。 (さらに読む)
基本書や予備校本を読むとき、マークをしながら読むと思うのですが、例えば、問題提起は何色、定義は何色、など決めていましたでしょうか。また決めていたら色を教えていただきたいです。
伊藤たける先生と同じにしたくて笑
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、伊藤講師のマーキング時をお伝え申し上げます。ご参考になれば幸いです。
-----
問題提起やトピック:ピンク
肯定事情・普通のマーク:イエロー
暗記事項・定義・規範:オレンジ
反対説:グリーン
(さらに読む)
以下、伊藤講師のマーキング時をお伝え申し上げます。ご参考になれば幸いです。
-----
問題提起やトピック:ピンク
肯定事情・普通のマーク:イエロー
暗記事項・定義・規範:オレンジ
反対説:グリーン
(さらに読む)
初歩的な質問で失礼いたします。
現在、吉野先生のインプット講座を受講中です。
どのタイミングで短答過去問を解き始めたら良いのかが良くわかりません。
「編を全て終えてから」とか「章単位で講義を聞いたら取り組む」等、短答過去問にチャレンジするタイミングを具体的にご教示いただけますと幸いです。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ある程度まとまった単位で演習に取り掛かればよいので、特に基準はありません。「章単位」と言っても長さが全然違いますので単位として意味がないです。何度も繰り返して演習するのが大前提なので、貯めすぎては駄目です。2,3回講義を聞いたら該当箇所の問題を解く、くらいのペースで良いかと思います。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ある程度まとまった単位で演習に取り掛かればよいので、特に基準はありません。「章単位」と言っても長さが全然違いますので単位として意味がないです。何度も繰り返して演習するのが大前提なので、貯めすぎては駄目です。2,3回講義を聞いたら該当箇所の問題を解く、くらいのペースで良いかと思います。 (さらに読む)
論パタ民法2-4-1についての質問です。93条但書のYの反論を認めたら間違いですか。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
あてはめ次第では、反論を認めるという筋もあり得ると考えます。
答案例では、Xがまだ18歳であることや視野が狭そうであることを理由に反論を否定していますが、そのような評価をしないのであれば、反論を認めることも可能だと考えます。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
あてはめ次第では、反論を認めるという筋もあり得ると考えます。
答案例では、Xがまだ18歳であることや視野が狭そうであることを理由に反論を否定していますが、そのような評価をしないのであれば、反論を認めることも可能だと考えます。 (さらに読む)