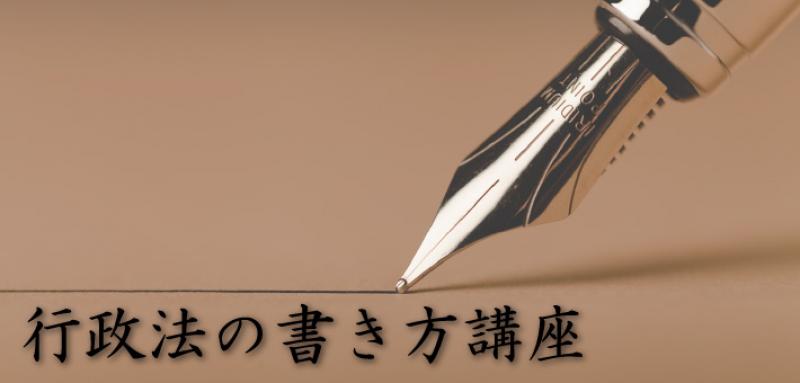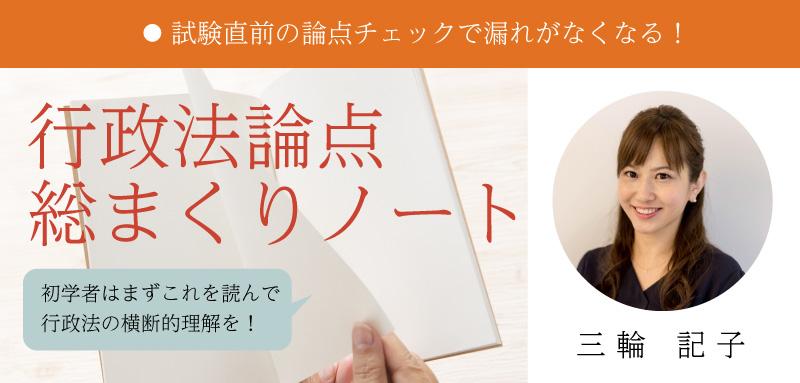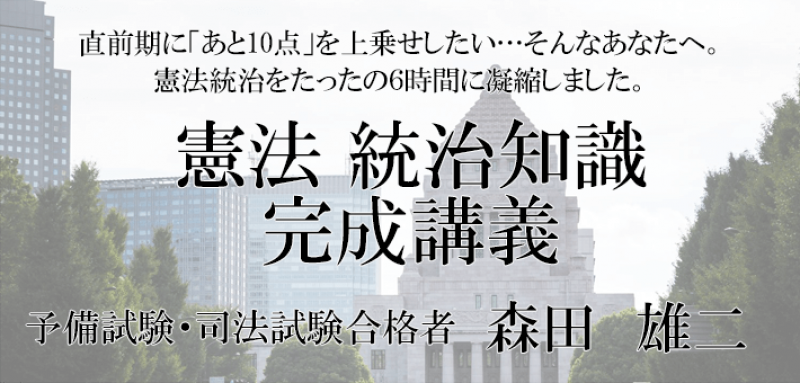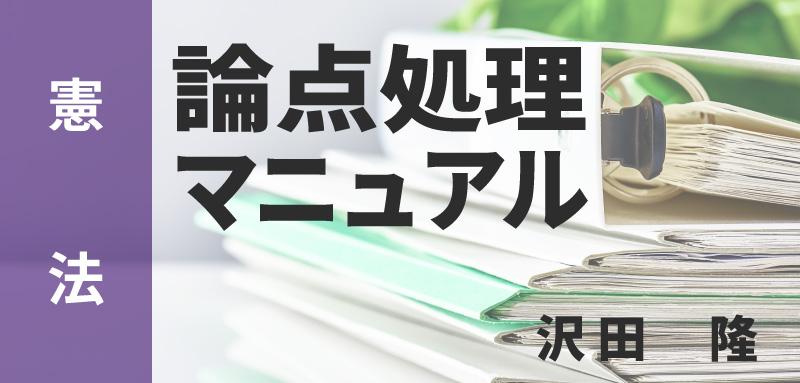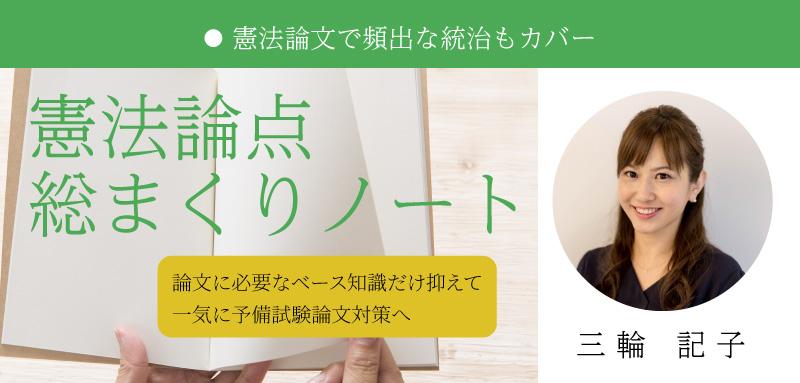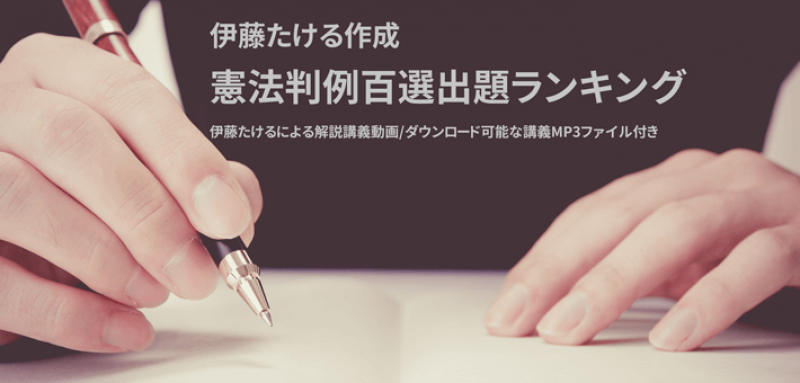あなたの本棚は大丈夫?合格教材の新定番を大公開〜公法編〜
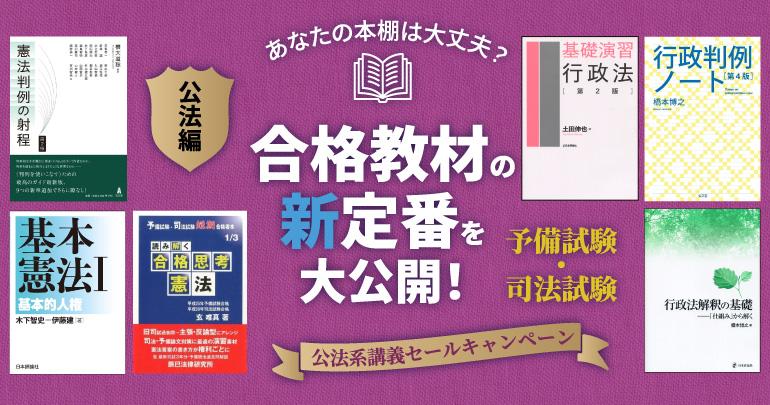
本試験まであと4ヶ月…合格には難しい教材が必要?
本試験が近づいてくると、自分の学習方法に自信がなくなってくるときがありますね。
約4ヶ月……まだできることがあります。
そんなときにもっといい教材があるのではないか?と色々と味見したくなりませんか。
司法試験の合格は難しい。だからこそ、難しい教材を効率よくマスターできる「ずるい教材」はないのかと、探しておられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は、現在の司法試験に合格するためには、難しい教材は不要です。
むしろ、基礎的な教材を繰り返し学習し、「基礎固め」をすることこそが、合格にとって必要なのです。
リベンジ合格者の多くも、合格した年は「おもしろいと思う勉強ではなく、ひたすら基礎をやっていた」と語っています。
合格教材の新定番を大公開!
弊社では、BEXAの7万件をこえるデータを元に、販売データやべクサの講師が集計したデータと売れ筋の講義から分析しました。
そこで、伊藤たける先生や剛力先生など講師の観点を加え、適宜実務化をはかった新定番を公開します!
合格へのロードマップ〜合格教材の新定番〜(公法系)
今回は公法系の合格教材の新定番を大公開します。
※次回、刑事系と続きますのでお楽しみにしてください。
表の見方
★:マスト教材(ほとんどの合格者受験生が取り組んでいる)
◎:不得意だったらやっておいた方が良い教材
◯:やりましょう(時間がなかったらやらなくていい)※滑りそうだったらやった方がいい
△:時間がない人は後回しの教材
✖️:気にしなくていい
行政法
多くの受験生は、行政法と刑事訴訟法で失点をしないように足場を固めています。
そのため、行政法をまっさきにできるようにすることが重要。なおかつ、普通の受験生よりも、一歩だけ前に出ればOKです。
論点自体は多くないので、まずは定番教材で差を付けられないところを目指しましょう。
- 基本書
- 基礎演習
- 予備・司法試験の過去問
「1.基本書」の定番は『基本行政法』です。
もし、サクハシなどの『基本行政法』以外を既に使っている場合は、買い替える必要はなく、行政法解釈の基礎を用いれば良いです。
かつて定番であった『事例研究行政法』は、過去問数が増えた現在では、やや優先順位が下がります。(アドバンスレベルです)
これに加えて、少しだけ差をつける必要があります。
差をつけるためには、あてはめで差をつけることが大切になってきます。
そのためには、判例をパターン化して学習すると、なお安心です!
そういった意味で、判例は『○』になっています。
→事案と結論をおさえた上で、理由づけをおさえ、そして結局結論に至った過程で重要視された事項は何かを理解することが大切です。
★行政法百選おすすめ講座〜公法系1位の愛川先生がコスパ良く『判例のモデル化』をお教えします〜
残り4ヶ月なにからやるべきか悩んでいる人
○過去問を極めましょう、特に予備の過去問を重点的にやりましょう!
→やることで、処理手順が身につきます。
○行政法は短期間で一気にやると理解が深まりやすい
→分割で勉強するのではなく、通しでやることが大切!
○判例百選は、なにが載っているか理解することが大事
ぜその判例がその百選に載っているかを考え、載っている判例をきちんとカバーするということを意識しましょう。
→判例百選読みものとして読むと、短答ができるようにもなります。
「ご好評につきOPEN SALE延長!」
憲法
憲法については、失点をしないことが重要です。
出題形式が主張反論型から意見書型に変わったものの、複数の立場を論じるという基本スタンスは全く変わっていません。
そのため、憲法では、最低でも、1つの事案を複数の立場から主張・反論ができるようにする意識が重要となってきます。
だからこそ、基本書や1つの立場から論じるだけの問題をやっても、試験対策としては不十分です。
そのため、複数の立場からの立論が必要な過去問こそが、もっとも優先順位が高くなります。
また、判例は、当事者が争っているポイントがわかりやすいことや、地裁、高裁、最高裁で判断が分かれたり、最高裁内部でも裁判官同士で意見が割れたりすることが数多くあります。
そのため、主張・反論を組み立てるためには、判例を要むことで、対立点(争点)の組み立て方のコツが理解できるのです。
さらに、憲法の場合、条文数が少なく、条文の内容も「学問の自由はこれを保障する」というような漠然としたものであり、
民法や刑法と比べて、条文を読むだけではその意味が分かりません。
そのため、この抽象的な条文にどのような法的意味があり、どのような判断枠組み(違憲審査基準)を設定するか、あてはめでどのような事実を用いるのかという解釈論こそが、答案のポイントになります。
だからこそ、判例を読むことで、これらの条文の保障内容や、違憲審査基準、あてはめの作法を学ぶことが重要になるのです。
残り4ヶ月なにからやるべきか悩んでいる人
○百選は、この時期からならば当てはめの参考程度でよい<優先度は高くない>
他の科目と比べると受験生のレベルが低いため、受かるのにに何が要求されているか、それはある程度の答案の形を守っておくことと問題文の事案を使うべきところで使って、自分の言葉で評価ができることが大切です。
(例)目的手段審査のあてはめの部分で手段の正当性や相当性など自分の言葉で評価が入れられることが大切
→過去問演習をやっておけば、どの事案をどこで使うのか、ある程度習得できます。
司法試験の過去問と採点実感を用いれば、ある程度の合格レベルの答案が見えてきます。
○予備・司法試験の過去問で落ちない答案(40点)を目指そう
司法試験過去問行い、余裕があったら予備過去問をやるべきです。
上位答案の分析して自分に当てはめをどういう風に持っていくかを意識してどう守るかを意識したほうが良いです。
論文対策で判例百選を使うのは難易度が高いので、採点実感を読めば、試験員にとって何をやっていけないかわかるため学びましょう。
YouTubeLIVE : いよいよ年明け!本試験まで4ヶ月の過ごし方!(司法試験編)〜合格教材の新定番を大公開!〜
<伊藤たける先生 ✖️ 吉野勲先生 ✖️ 剛力大先生 >が合格教材の新定番を考えます!
行政法は【4:33〜15:13】、憲法は【1:20:35〜】で詳細に話してます。ぜひご参考にしてください。
公法系講座を受けて対策をしよう!〜公法系講座セールキャンペーン〜
そうはいっても、あと本試験まで4ヶ月ありません。
自分で取り組むには時間がないですし、想像するだけで量が膨大で過酷ではないですか?
そんなときに経験豊富な講師が重要な部分を講義している講座を受講することが合格への近道になるのです!
そんな方のために「公法系講座セールキャンペーン』を実施(2月8日〜2月14日)します!ぜひ活用して、「合格への近道」をつかみとりましょう!
公法系講座セール一覧
〜行政法〜
〜行政法(過去問)〜
〜行政法含む講座〜
〜憲法〜
〜憲法(伊藤たける)〜
2022年2月8日 BEXA事務局
役に立った:2