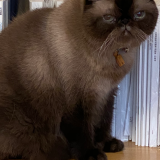未回答の質問
平成 30 年予備試験商法 設問2 について、参考答案では「Bは 356 条 1 項 2 号に該当する利益相反取引を行っているが、株主総会での承認を経ていないため、法令違反行為があり、任務懈怠がある。」としていますが、問題文では「なお,本件賃貸借契約の締結に当たり,甲社は,会社法上必要な手続を経ていた。」とあるので誤りだと思います。
参考リンク
参考リンク
[刑法]共犯者間における抽象的事実の錯誤について質問です。
かかる論点は、どの要件充足性を判断する上で問題となる論点なのでしょうか?
共謀(=特定の犯罪についての意思連絡)が認められるか。という問題なのでしょうか?
だとすれば、共同正犯の要件たる②共謀に基づく実行行為を認定する前に書くこととなってしまい、錯誤であることを述べづらいので困っています。
答案を実際に書く際の視点からご教授願います。
刑法では、体系上の位置づけを常に意識する必要がありますから、大変いいご質問だと思います。
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。 (さらに読む)
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。 (さらに読む)
未回答の質問
お世話になっております。令和4年度民法設問2について質問です。取得時効が認めれるかにおいて、185条「新たな権原」の検討前に187条1項「承継人」に該当するかを論じる必要はないのでしょうか。
参考リンク
参考リンク
未回答の質問
これだけ!75の刑法の第7回で述べられていた2項強盗についてです。
財産的利益の移転の確実性・具体性が認められない場合、「暴行・脅迫」の要件が切れ、2項強盗の未遂も成立しない。との説明がありましたが、これは、実行の着手が認められない=不能犯となる。との理解でよいのでしょうか?
また、その場合、単なる暴行・脅迫(傷害、殺人)罪となるという帰結でしょうか?
各科目について、コア知識編はどのように活用するのでしょうか?対策講義との関係や勉強する順番など教えて下さい。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
まずは各科目コア思考編を完璧に習得することを意識してください。その上で、周辺の知識を習得するために、コア知識編をご活用ください。
なお、この周辺の知識の習得のフェーズは、演習書に網羅的に取り組む等でも代替可能です。どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
まずは各科目コア思考編を完璧に習得することを意識してください。その上で、周辺の知識を習得するために、コア知識編をご活用ください。
なお、この周辺の知識の習得のフェーズは、演習書に網羅的に取り組む等でも代替可能です。どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
【ご案内】法改正レジュメを追加しました|民事訴訟法(知識編)とのことで、内容を確認しました。
これは、全て令和7年度の試験に反映される(令和7年1月1日に施行済み)の内容なのでしょうか。
参考リンク
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。
担当講師に確認をいたしましたところ、
「ご認識の通りで間違いない」とのことでございます。
ご参考になれば幸いです。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
担当講師に確認をいたしましたところ、
「ご認識の通りで間違いない」とのことでございます。
ご参考になれば幸いです。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
お世話になっております。令和6年まで解説動画を出していただきありがとうございます。今後、令和7年の解説動画が追加される予定はありますでしょうか。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
-----
令和7年度の予備試験過去問講義については、追加収録を予定しております。販売方法については未定ですので、決まり次第全体へ向けてアナウンスさせていただきます。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
-----
令和7年度の予備試験過去問講義については、追加収録を予定しております。販売方法については未定ですので、決まり次第全体へ向けてアナウンスさせていただきます。 (さらに読む)
75の製本化をしてもらえないでしょうか。
参考リンク
参考リンク
この度はご要望をいただきありがとうございます。
講師及び担当部署とも共有し、検討して参ります。
より良い講座提供に努めて参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
貴重なお声をいただき、ありがとうございました。 (さらに読む)
講師及び担当部署とも共有し、検討して参ります。
より良い講座提供に努めて参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
貴重なお声をいただき、ありがとうございました。 (さらに読む)
未回答の質問
いつもお世話になっております。H29年予備試験刑法に関する質問が2点あります。
①間接正犯において、正犯意思という主観から検討する理由を教えてください。
②剛力先生の答案では、2(1)ウ「甲の上記行為に間接正犯としての殺人の実行の着手が認められる」とありますが、今回、間接正犯の実行の着手は問題とならないとの認識であっていますでしょうか。「殺人の実行行為性が認められる」としてもいいでしょうか。
参考リンク
参考リンク
民法59ページにおいて「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とありますが、423条の5柱書に「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、」と規定されているので、受益者が善意の場合は転得者に対しても詐害行為取消請求することはできないと読めます。
受益者善意、転得者悪意の場合に、転得者への詐害行為取消請求は認められるのでしょうか?
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
民事訴訟法問題編p.40について、
① 設問中、イの選択肢の記述が崩れています。
② エの解説 重複起訴が重複基礎になっています。
また、当該ページに限らず、全体的に誤字脱字が見受けられますので、可能であれば全体的に校閲の上、レジュメを修正いただけないでしょうか。
(下4法セットで購入いたしましたが、民訴に限らず、他教科についても同様の指摘が可能です。)
参考リンク
参考リンク
この度はテキストの不備に関しまして、ご不便をおかけしており申し訳ございません。
ご指摘をいただきましてありがとうございます。
該当箇所につきましては、誤植の確認をいたしました。
担当部署に申し伝え差し替え対応をして参ります。
お時間をいただく可能性がございますが、差し替え時にはご受講ページの「お知らせ」よりアナウンスいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけしているところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
ご指摘をいただきましてありがとうございます。
該当箇所につきましては、誤植の確認をいたしました。
担当部署に申し伝え差し替え対応をして参ります。
お時間をいただく可能性がございますが、差し替え時にはご受講ページの「お知らせ」よりアナウンスいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけしているところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
行政法の判例のテキストがありません。
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
判例編につきましては、
「行政判例ノート」(市販の教材)をお手元でご覧いただきながらご受講いただくことが前提の講座となっております。
詳しくは、下記講座案内ページの「受講形式」をご確認いただけますと幸いでございます。
◆短答思考プロセス講座 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
https://bexa.jp/courses/view/265
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
判例編につきましては、
「行政判例ノート」(市販の教材)をお手元でご覧いただきながらご受講いただくことが前提の講座となっております。
詳しくは、下記講座案内ページの「受講形式」をご確認いただけますと幸いでございます。
◆短答思考プロセス講座 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
https://bexa.jp/courses/view/265
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
レジュメのある年とない年がありますが、アップロードミスということはございますか?
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
レジュメに関しましては、
ご受講ページ>この講座に関するお知らせに記載がございます。
2025年1月31日
【配信情報】付属レジュメの追加配信予定・民法H24レジュメ差し替え予定のお知らせ
をご確認いただけますと幸いでございます。
-------------------
【付属レジュメ情報】付属レジュメ(答案構成/論点解説)は一部付属していない年度がございます。(※1/31時点)
多くのご要望を受け、2月中に全年度分の付属レジュメをを配信予定です。
また、民法 平成24年度のレジュメに不備があったため、2月中に差し替えを予定しております。ご不便をおかけし申し訳ございません。 (さらに読む)
レジュメに関しましては、
ご受講ページ>この講座に関するお知らせに記載がございます。
2025年1月31日
【配信情報】付属レジュメの追加配信予定・民法H24レジュメ差し替え予定のお知らせ
をご確認いただけますと幸いでございます。
-------------------
【付属レジュメ情報】付属レジュメ(答案構成/論点解説)は一部付属していない年度がございます。(※1/31時点)
多くのご要望を受け、2月中に全年度分の付属レジュメをを配信予定です。
また、民法 平成24年度のレジュメに不備があったため、2月中に差し替えを予定しております。ご不便をおかけし申し訳ございません。 (さらに読む)
商法(会社法)レジュメ第3 機関
第3-1 P.1について、
取締役会設置会社においては取締役を3人以上置くことが必要的ですが、
根拠規定が331条4項となっています。
正しくは331条5項ではないでしょうか。
誤植の可能性があると思い、投稿いたします。
参考リンク
参考リンク
ご連絡をいただきありがとうございます。
講師に確認をいたしましたところ、
ご指摘のとおり331条5項であるとのことでございます。
お詫びして、訂正いたします。
この度は、ご指摘をいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
講師に確認をいたしましたところ、
ご指摘のとおり331条5項であるとのことでございます。
お詫びして、訂正いたします。
この度は、ご指摘をいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
経済法速習講義第2版のp58(2)の2文目で、「指名業者を意のままに操る」という部分がピンときません。非指名業者がどういう意味で指名業者を意のままに操っているといえるのでしょうか?個別調整の前提として基本合意の存在が不可欠なものとなっていることから、何となくは理解できる気もするのですが、言語化ができません。回答よろしくお願いします。
令和6年分のレジュメ&答案、憲法と商法のレジュメ&答案の掲載は1月からになる旨のお知らせを見かけましたが、具体的には1月何日頃にテキストと講義が配信されるのでしょうか?
参考リンク
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
令和6年分のレジュメおよび答案につきましては、月内を目途に準備を進めております。
1月末にはご案内できるかと存じますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
令和6年分のレジュメおよび答案につきましては、月内を目途に準備を進めております。
1月末にはご案内できるかと存じますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)