
SALE 4月13日まで公法系上位1%が作った 予備試験過去問 憲法
大谷大地『公法系上位1%が作った 予備試験過去問 憲法』
体験動画・資料
○短期間(約2ヶ月)で憲法論文の力を飛躍的に伸ばしたポイントは?
令和5年予備試験、令和6年本試験に最終合格された方に憲法論文の対策法をインタビューしました。
学習時間:平日朝夜で3~5時間程度/休日3~8時間程度
予備試験2回目での合格
令和4年論文成績C~F(憲法はE)
→短答前後まで憲法論文対策は一切せず、令和5年憲法でA評価とジャンプアップ
Q:短答試験後に憲法論文対策をされたんですか?
そうです。前年、憲法論文はE評価と大爆死だったというのもあって、不合格後は憲法論文は半ば諦め、令和5年7月時点まで判旨と百選解説の読み込みしかしていませんでした。問題演習や起案は一切していません。
短答前までに憲法以外はある程度目途を立てて、短答後は憲法過去問だけを繰り返す学習を中心にしていました。平日は毎日憲法論文の構成・起案・分析、休日に他の科目の論文準備と明確にわけてました。
合格した人の「憲法は過去問だけやれ」のアドバイスを信じ、ひたすら繰り返しましたね(最大で1問10周とか)。結果として無駄なことをせずに論文で高評価を得られました。
Q:どういったことを意識して過去問に取り組みましたか?
私が過去問で意識したのが、問題の事実をどうやって憲法論に引き上げるかという点です。
憲法がなぜ対策しづらいと感じるのかというと、問題の想定がしづらいからだと思います。
たとえば、刑法なら正当防衛が出る、民事訴訟法なら確認の訴えの利益が出るって明確に論点がイメージできてそれを踏まえて問題の想定をしますが、憲法は表現の自由が出るって言われても「で?」ってなってしまいます。
そのため別のアプローチが必要になるって感じていて、どうせ問題の想定ができないんだから、事実→憲法論の訓練に集中することにしました。
予備試験論文はよくできていて、同じ問題でも人によって構成や重視する事実が微妙に異なるので、1つの問題から憲法論に引き上げる複数の方法を学ぶことができました。
加えて、出題パターンって言っていいかわかりませんが、問題文から試験委員の問題意識がどこにあるのかを発見できるような感覚も出てきました。
これも感覚的ではありますが、過去問も横断的にやると年度相互に理解が深まるのではないかと思います。
○事実から憲法論への引き上げであなたの憲法的センスを鍛えよう
憲法以外の科目では「○○という論点の要件はこれとこれで、この要件で判例・学説があるな」といった知識の引き出しを繰り返すことで問題の想定ができますが、憲法はそもそもこのような構造にはなっていません。
憲法以外の科目と同じような論文対策だと学習効果が小さくなる可能性があります。
その一方で、合格者インタビューにもあるとおり問題文の事実から憲法論に引き上げる訓練はあなたの憲法的センスを鍛え、大きな学習効果が見込める方法です。
特に予備試験過去問は様々な主張・反論方法が可能であり、過去問だけを深く繰り返すことで、あなたの目の付け所・事実の利用の仕方・答案バランスなど総合的な憲法的センスを鍛えることが可能です。
○予備試験過去問を題材に上位合格者の思考過程を0から100まで!
本講座は、本試験公法系上位1%で合格された大谷大地先生が問題文を読むことから答案の完成までの一連の思考過程をすべて解説する講座です。題材は、平成27年~令和6年の予備試験憲法過去問です。
問題文の事実の詳細な言及や採点者が見るポイントの解説、解説にもとづく講師オリジナル答案も提示しています。
さらに、インプットが必要な知識の明確化や合格ラインの予想をもしてしまう講座です。本講座を受講すれば、過去問憲法であなたの憲法的センスを鍛えることが可能になります。
○本講座の特徴
・問題文全文への詳細な言及・採点者が見るポイントの解説
本講座は、予備試験憲法の平成27年~令和6年の10年分の過去問問題文を大谷先生が分析、採点者が見るポイントの解説をします。
どういった事実が採点者が汲み取ってほしい事実なのか、そのポイント、見つけ方を解説します。
・事前インプットが必要な知識の明確化・「添削」実感に基づく的確な合格ライン予想
憲法でももちろん知識、特に判例知識が必要ですがどの程度のものが必要なのかの線引きが難しいですが、本講座では大谷先生がその線引きについて言及します。
また、どの程度まで解答することが合格ラインに必要なのか、そのラインの予想も行います。
・講師作成フル答案付き
本講座は起案面までもフォローします。
大谷先生が受験生時代に準備していた論証やあてはめのポイントといった、上位合格者のノウハウも提供します。
〇受講条件

講座形式
販売価格
29,800円(税込)
▼【大谷大地×伊藤たける】令和5年試験での対談動画はこちら
大谷先生の講師紹介ページはこちら
■関連記事
カリキュラム
-
大谷大地『公法系上位1%が作った 予備試験過去問 憲法』 プランのカリキュラム
- 講義時間: 約12時間45分
- 配信状況: 全講義配信中
大谷大地『公法系上位1%が作った 予備試験過去問 憲法』 講座数 21 12時間45分
-
第0回 オリエンテーション「過去問演習の戦術」40分
-
第1回 平成27年_解説編34分
-
第2回 平成27年_解答編24分
-
第3回 平成28年_解説編43分
-
第4回 平成28年_解答編31分
-
第5回 平成29年_解説編42分
-
第6回 平成29年_解答編35分
-
第7回 平成30年_解説編43分
-
第8回 平成30年_解答編34分
-
第9回 平成31年_解説編45分
-
第10回 平成31年_解答編51分
-
第11回 令和2年_解説編43分
-
第12回 令和2年_解答編30分
-
第13回 令和3年_解説編40分
-
第14回 令和3年_解答編33分
-
第15回 令和4年_解説編44分
-
第16回 令和4年_解答編29分
-
第17回 令和5年_解説編32分
-
第18回 令和5年_解答編32分
-
第19回 令和6年_解説編37分
-
第20回 令和6年_解答編23分
講義を閉じる
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0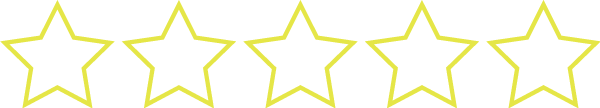
おすすめコメントはありません。
講座に悩んだら

祝!天皇誕生日と3連休にちなんだ【特別企画】☆7%OFFクーポン進呈中!_2/21~24限定
天皇誕生日と3連休にちなんだ特別企画<2/21-24限定>☆ 全講座及びセール価格からもさらに使える7%OFFクーポンです! (※ただし、一部プランを除きます)




 オリエンテーション「過去問演習の戦術」
オリエンテーション「過去問演習の戦術」







