
論文処理手順講義 2025
沢田隆『論文処理手順講義 2025』
※「論文処理手順2025(レジュメ)」がついてくるセットプランです。
講師推奨プラン
この講座の他のプラン
体験動画・資料
司法試験学習の「隙間」を埋める唯一の教材
司法試験・予備試験の学習を進める中で、こんな悩みを抱えていませんか。
・「模試や過去問演習を繰り返しているが、なぜ評価が低いのか分からない」
・「合格答案と自分の答案の違いが見えず、何を改善すればいいのか分からない」
この問題の原因は明白です。
従来の学習法では、下記①〜③の間にある 「思考過程」や「処理手順」 の指導が不十分なのです。
①知識のインプット(入門)
②論点や判例の理解(論証パターン・判例学習)
③アウトプット(演習)
この隙間を埋めるために開発されたのが、「論文処理手順」 といわれる本講座です。
司法試験学習の重大な欠陥!答案作成の「処理手順」が明文化されていない
従来の学習法の問題点を整理すると、以下のようになります。
1. 入門・基礎学習では答案作成には至らない
→どれだけ基本書や講座で知識を詰め込んでも、それを答案に反映させる方法までは教えてくれません。
2. 演習を繰り返しても「正解」が分からない
→模範答案を書き写しても、それがどうして評価されるのか、どのように思考を進めれば良いのかが不明確です。
3. 「処理手順」の指導が抜け落ちている
→答案作成で最も重要な「思考過程」や「処理手順」は、従来の学習法では「見て学べ」とされており、明文化されていないため、多くの受験生が迷子になります。
この状況下で、早期に処理手順の重要性に気づき、自力でその方法を編み出せた人だけが短期合格を果たします。一方で、気づけない受験生は学習の迷路に迷い続けるのです。
「論文処理手順」で学習の隙間を完全に埋められる!
本講座は、司法試験学習の隙間を埋めるために、講師自身が上位ロー・予備試験・司法試験の短期合格するために、数年かけて体系化した「論文処理手順」を元にしています。
この教材では、従来の学習法では教えられなかった「答案作成の処理手順」を明文化し、誰でも学べる形に落とし込んでいます。
講座の特徴
1. 具体性と網羅性
答案作成に必要な「処理手順」を明確にし、学習の指針を具体化します。
2. 実践的なアプローチ
答案作成に必要な「処理手順」を明確にし、学習の指針を具体化します。
3. 個別指導に近い学習を実現
法科大学院のゼミや個別指導を受けられず、優秀な人に答案をみてもらえない方でも、独学で学習の隙間を埋められる内容となっています。
その理由は、講師自身が、上位ロー・予備試験・司法試験の合格のために数年をかけて作成した教材だからです。
合格までに必要な道のりを、より具体的かつ細分化して提供しています。
本講座の構成
※プランによっては、附属しません。
〇講義(解説)編:レジュメの内容を深掘りし、具体的な活用法を網羅的に解説
〇実践編:実際の過去問を用いて答案作成力を鍛える演習
〇論点処理マニュアル(全科目):論証パターンを網羅した教材で応用力を養成
実績と信頼
●700人以上の司法試験合格者 が、この教材を活用して司法試験合格を実現!
司法試験受験資格の有無を問わず購入できる教材にもかかわらず、予備試験の合格率(4%)を大幅に超える水準であり、高い信頼と実績を誇っています。
処理手順ノートがなぜ選ばれるのか?一部を公開!
◆ 法的思考(リーガルマインド)が身に付く!
【憲法】 法的思考の可視化
本講義では、単に論点ごとの処理手順を解説するだけでなく、受験生が曖昧にしがちな抽象概念を可能な限り可視化し、利用できるよう工夫をしています。抽象概念を言語化できることも法的思考の1つと考え、可能な限り受験生が試験で利用できるよう工夫をしています。
▶▶レジュメはこちらからダウンロード
◆ 科目ごとの処理手順がわかる!
【民法】答案の型から逆算した総合的な処理手順!
民法では、「要件効果を意識すべき」といわれますが、本講義では「答案の型」を通して要件効果の意識が自然と身に付く工夫をしています。答案の型+要件効果の意識=ゴールの合格答案がイメージできるだけでなく、ゴールから逆算することで覚えている知識の整理整頓を行うことが可能になります。本講義により、民法の総合的な処理手順を習得することが可能になります。
▶▶レジュメはこちらからダウンロード
【民法】 誤解されやすい答案の改善案も提案
法的思考と言っても答案で表現できなければ意味がありません。本講義では、評価されづらい悪い書き方の例を提示しつつ、その改善案を提案しています。
▶▶レジュメはこちらからダウンロード
【刑法】答案のパターンに対応する類型別処理手順
刑法は、出題パターンによって答案を対応させる必要があります。本講義では、総論型・各論型と複数の出題パターンを区別し、それぞれに対応した処理手順を解説します。
▶▶レジュメはこちらからダウンロード
こんな方におすすめ
〇複数回受験を経験し、行き詰まりを感じている方
〇短期合格を目指したい方
〇個別指導やゼミに頼らず自力で突破したい方
本講座を通じて、司法試験合格までの「隙間」を埋め、答案作成に必要な全てのスキルを手に入れて、司法試験最短合格に近づきませんか。
受講条件

・講座形式
・通常販売価格
〇論文処理手順講義 2025:109,000円(税込)
※「論文処理手順2025(レジュメ)」とのセットプランになります。
〇【対象者:論文処理手順2025購入者】沢田隆『論文処理手順講義 2025』:96,200円(税込)
※「論文処理手順2025」は附属しませんので、ご了承のほどお願いいたします。
◆旧「論文処理手順講義」ご購入者様限定でアップデートプランをご用意!
カリキュラム
-
沢田隆『論文処理手順講義 2025』 プランのカリキュラム
- 講義時間: 約15時間55分
- 配信状況: 全講義配信中
【総論】論文処理手順講義 2025 講座数 3 1時間
-
第1回5分
-
第2回30分
-
第3回25分
講義を閉じる【憲法】論文処理手順講義 2025 講座数 3 1時間41分
-
第1回34分
-
第2回43分
-
第3回24分
講義を閉じる【民法】論文処理手順講義 2025 講座数 3 1時間51分
-
第1回34分
-
第2回42分
-
第3回35分
講義を閉じる【刑法】論文処理手順講義 2025 講座数 3 1時間25分
-
第1回35分
-
第2回30分
-
第3回20分
講義を閉じる【行政法】論文処理手順講義 2025 講座数 4 1時間30分
-
第1回20分
-
第2回23分
-
第3回20分
-
第4回27分
講義を閉じる【商法】論文処理手順講義 2025 講座数 2 1時間8分
-
第1回35分
-
第2回33分
講義を閉じる【民事訴訟法】論文処理手順講義 2025 講座数 2 1時間33分
-
第1回29分
-
第2回64分
講義を閉じる【刑事訴訟法】論文処理手順講義 2025 講座数 3 1時間24分
-
第1回35分
-
第2回34分
-
第3回15分
講義を閉じる【実践編】論文処理手順講義 2025(平成30年予備試験解説) 講座数 7 4時間23分
-
民法49分
-
商法27分
-
民事訴訟法38分
-
刑法33分
-
刑事訴訟法28分
-
憲法40分
-
行政法48分
講義を閉じる
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0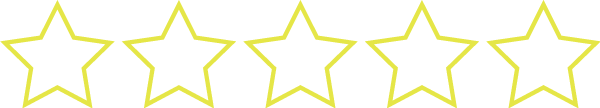
おすすめコメントはありません。
講座に悩んだら
沢田隆『論文処理手順講義 2025』
※「論文処理手順2025(レジュメ)」がついてくるセットプランです。
【対象者:論文処理手順2025購入者】沢田隆『論文処理手順講義 2025』
※「論文処理手順講義2025(レジュメ)」が附属されないプランになりますので、ご注意ください。




 総論:論文処理手順講義とは
総論:論文処理手順講義とは





