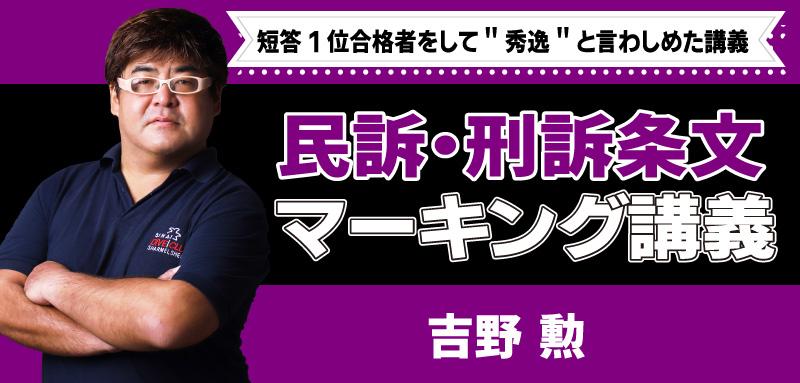短答試験直前期でもまだ伸ばせる!「理解を深める講座」で点数アップを目指そう

こんな悩みはありませんか?
・時間がないから合格できるか不安......
・短時間で「知識の総チェック」ができる教材が欲しい!
短答式試験合格へ。今こそ本気で走り抜けるとき!
令和6年度の予備試験短答式試験の合格率はわずか21.9%。
この狭き門を突破するには、今この瞬間からの行動が鍵になります。
短答は、努力がそのまま結果に直結する試験です。だからこそ、最後の1日まで本気で取り組むことが合格を引き寄せる最大のポイントとなります。「もう無理かも…」と思ったときこそ踏ん張りどき。 諦めない人が、合格を掴み取るのです!
この直前期の追い込みこそが点数を最も伸ばし、さらに、ここで積み上げた知識は、論文試験にもつながる力になります。
合格への道は、まだここから開ける。この記事では、短答試験までの仕上げ方をお伝えします!
過去問は解ける。でも本番で点数がとれない方へ
過去問では点数が取れていても、大事な本番で点数が取れない、、、実は、記憶力の良い人は、この壁にぶち当たる傾向があります。それは、答えを「知識」として丸暗記してしまっているからです。合格するためには、「知識を覚える」のではなく、「理解を深める」ことが重要です。
例えば、自転車は一度乗れるようになったら乗れなくなるのは不可能、最初はどんなコケかたをしても一度乗れるようになったらちゃんとコケないようになります。同じように、暗記するだけでなく、理解ができれば、いろいろな問題が解けるようになるのです。
では、丸暗記ではなく「理解を深める」ためには?

吉野勲 シン・王道シリーズ『論文突破道場』の「短文事例問題」がおすすめ!
吉野勲 シン・王道シリーズ『論文突破道場』は、以下4編で構成されている講座です。
②短文事例問題(約47時間)
③予備試験過去問完成(約69時間)
④旧司法試験過去問セレクト(約55時間)
「知識を持っていても、理解できていなければ知らないのと同じ!」
「シン・王道シリーズ 総まとめ150」の短文事例問題は法的思考が身につき、短答試験対策にも最適な講座です。
短文事例問題(約47時間)は論文段階への橋渡しとなる講座。「事例問題に触れる」ことで短答対策に活かせる内容です。
多くの受験生が短答後の「論文の高い壁」に苦戦している中、その高い壁を超える対策は早い段階から必須と言われいてます。「短文事例問題」は短答から論文へ移行する際の「補助ステップ」がいるという発想から生まれた業界初の講座!
この「高い壁」に苦戦しないために、短答対策の時期から「短文事例問題」に触れることが大切です。「短答事例問題」を7科目やりきることで先を見据えた短答試験対策を実践しましょう。
とにかく忙しくて時間がないあなたへ

1科目18時間以内の講義時間!忙しいあなたにおすすめなのは、短答思考プロセス講座!
予備試験短答で確実に合格するには、法律科目で150点以上の得点が目安。
つまり、1科目20点を下回らない学習戦略が必要です。
例えば、商法は特に難易度が高く、会社法が壁になりがち。そのため、「商法総則・手形小切手」で満点(8点)を取り、会社法で半分(12点)を確保する戦略が有効です。
この講義では、「条文を読み込めない」「読み込む時間のない」受験生のために、事前に剛力先生がまとめたレジュメを提供し、これを元に解説をすすめます。
レジュメは条文の体系を念頭に、必要な「手続知識」や「判例知識」をまとめた内容のため、短答で点数を取るために必要十分な内容を網羅。「レジュメ+剛力先生の解説」を受ければ、全体像を把握することができると同時に、短答に必要な知識を「整理された状態」でインプットすることができる講座です。
直前期の「知識の総チェック」がしたいあなたへ
条文マーキングがおすすめ!
「条文マーキングシリーズ」は、短答プロパー知識をピックアップした講座です。短時間で効率よく得点力を上げたい方に最適な内容となっています。
この講座では、条文の趣旨や文言の確認に加え、判例や周辺知識を関連づけながら、各科目を体系的に「知識の総チェック」をすることができます。そのため、六法、基本書、判例の要点を確認でき、高い学習効果が期待できます。また、1科目あたり4時間~17時間の受講時間のため、効率よく学習ができます。直前期の「知識の総チェック」に最適な講座です!
短答試験直前期でもまだ伸ばせる!
予備試験の短答式は、情報量が多く、合格率も決して高くありません。だからこそ、「効率よく、正確に、深く理解すること」が最大の鍵になります。今、「時間がない」「不安だ」「苦手分野がある」──そのすべては、正しい方法で向き合えば乗り越えられます。合格に必要なのは、「天才的な才能」ではありません。正しい方向へ、本気で踏み出す勇気と継続する力です。
さあ、あと一歩。本気で走り抜けたその先に、あなたの「合格」が待っています。
最後まであきらめずに、点数アップを目指しましょう!
【 参考動画】短答は何周回せばいい!ということではない!
役に立った:0