
違いがわかる・迷わず解ける!短時間で「財産犯」マスター
藤澤潤『違いがわかる・迷わず解ける!短時間で「財産犯」マスター』
体験動画・資料
◆こんな悩み、ありませんか?
窃盗、詐欺、横領、背任…どれも似ていて、違いがよくわからない。
そう思って、なんとなく財産犯を後回しにしていませんか?
実際、本試験やローの定期試験で問われたとき、
・窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いに迷って当てはめがブレる
・不動産なのに窃盗罪で書いてしまった
・欺罔行為がないのに詐欺罪で書いてしまった
・横領と背任の判断基準が整理しきれない
こうした混乱に陥ることは、決して少なくありません。
財産犯は、類型ごとの構成要件が微妙に違い、しかも「似ているのに違う」犯罪が横に並んでいる分野。
何を基準に区別すればいいのかが曖昧なまま学習を進めてしまい、
見たことある論点なのに試験で点が伸びない、という事態に陥りがちです。
さらに厄介なのは、各犯罪特有の構成要件、たとえば「不法領得の意思(窃盗)」「欺罔(詐欺)」「委託関係(横領)」などをきちんと整理していないと、 不意に問われた時、「なんだっけ?」「どっちだっけ?」と本番でフリーズしてしまうこと。
体系的な理解が追いつかないまま、過去問を解いてもモヤモヤが残る。
そして「やっぱり財産犯、苦手かも…」というループに入ってしまうのです。
◆理念・コンセプト
財産犯を“比較”と“イメージ”で整理し、短答も論文も迷わない理解を。
しかし、それらの違いを「なんとなく」で捉えていると、ひねった短答や実戦的な論文問題に対応できません。
本講座では、
①各犯罪類型の異同を一覧表で整理
②一覧表や具体的事例を用いながら、構成要件をイメージ化
この2つのアプローチで、暗記ではなく“使える知識”として理解を定着させます。
短答では、マイナー判例や事例型問題での判断力がつき、
論文では、対立軸を意識した説得的な論述力が身につきます。
「財産犯がなんとなく苦手」を、「財産犯は自信をもって扱える」へ変える講座です。
◆この講座で得られること
・犯罪類型の違いがスッと理解できるようになる
・短答のひっかけに対応できる「構成要件の意味理解」が身につく
・論文で求められる「対立軸」や「立場比較」が整理できるようになる
・ただの暗記から脱却し、「なぜそうなるか」を自分の頭で説明できるようになる
・財産犯が答案の中で“使える知識”になる
◆こんな方におすすめ
・財産犯が苦手で、いつも後回しにしてしまっている
・類型の違い(窃盗・詐欺・横領など)を明確に区別できるようになりたい
・短答でマイナー判例やひねりのある事例に対応できる力をつけたい
・論文で反対説を意識した論述が苦手
・判例や学説の立場を、なんとなく覚えているだけになっている
・現場対応力を高めて、本試験での“迷い”をなくしたい
◆講座の特徴
忙しい受験生向けに、基礎から応用まで短時間で効率よく学べる構成
犯罪類型ごとの“異同”を比較表で整理
窃盗・詐欺・横領・背任など、混同しやすい類型を横断的に比較。
各犯罪類型の共通点と相違点を整理し、理解を深める。
具体的事例と図解で、教科書的理解を“現場対応型”に
典型的な事例やパターンを使って、抽象的な条文理解を具体化。
「思い出す知識」から「使える理解」へ。
短答過去問解説付き
令和2年司法試験・予備試験の短答問題を解説し、本番での思考力を鍛える
講師インタビュー(Q&A)
Q.1 短答で財産犯はどのような問われ方をして、どこにつまずく受験生が多いですか?
典型的な事例で当該犯罪の成否が判断できる問題は正解率が高いですが、典型的な事例ではないもの、あまり教科書に載っていないマイナー判例になると正解率は低くなります。
Q. 2 論文で財産犯はどのような問われ方をして、どこにつまずく受験生が多いですか?
ところが、令和以降くらいから「〇〇について、反対説の立場を指摘しつつ論ぜよ」など、具体的な論点が問題文に掲示されたうえで、議論展開をさせる問題が出題され、傾向が大きく変化しました。たとえば詐欺罪であれば、欺罔行為を認める立場とそうでない立場両方で論じさせる問題などがあります。
つまり、自説だけを説明するだけでなく、反対説を意識して論理展開する能力も求められると言えます。そのため、大枠それ自体を外す答案は少なくなったようですが、他方で対立軸がよくわからない、あるいは深く論じられていない、といった答案が散見されます。
Q. 3「財産犯のイメージをつかむ力」はなぜ必要ですか?
つまり、それは各犯罪類型の異同やイメージを理解できていないからであり、「机上の学問」「教科書だけの勉強」で終わっているからです。
司法試験は短答はともかく、論文は典型的な事例が出題されるわけではなく、ひねった問題が出てきます。いわゆる現場思考が求められるわけですが、現場思考は「基本・典型」をイメージして、「基本・典型」とどこか異なり、どこか共通しているのか、というところを探りながら言語化することです。換言すると、「基本・典型」がイメージできていなければ、司法試験の問題を解くことは困難になります。
そのため、「イメージをつかむ力」は非常に大事だといえます。
Q.4 本講座では、どのような手段で上記のような受験生の悩みを解決しますか?
このイメージ化と異同が意識できれば、財産犯の苦手意識は払しょくできるかと思います。
講座内容
1.はじめに
2.財産犯の勉強方法
3.窃盗罪と詐欺罪
4.窃盗罪と横領罪
5.窃盗罪と占有離脱物横領罪
6.恐喝罪と強盗罪
7.横領罪と背任罪
8.具体的事例
9.令和2年短答刑法司法試験第2問/予備試験第8問
受講条件

講座形式
定価
7,600円(税込)
カリキュラム
-
藤澤潤『違いがわかる・迷わず解ける!短時間で「財産犯」マスター』 プランのカリキュラム
講義時間: 約1時間38分
配信状況: 全講義配信中藤澤潤『違いがわかる・迷わず解ける!短時間で「財産犯」マスター』
第1回 はじめに第2回 財産犯の勉強方法第3回 窃盗罪と詐欺罪第4回 窃盗罪と横領罪第5回 窃盗罪と占有離脱物横領罪第6回 恐喝罪と強盗罪第7回 横領罪と背任罪第8回 具体的事例第9回 令和2年短答刑法司法第2問/予備第8問
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0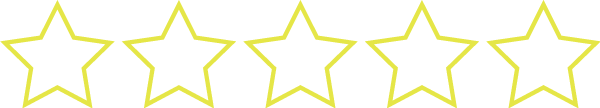
おすすめコメントはありません。
この講座を買った人はこの講座も買いました
講座に悩んだら

新春スタートダッシュSALE 短答対策編
今年こそ予備短答合格を目指すあなたへ!ライバルよりも先に、2026年のスタートダッシュをきって合格へ駆け抜けましょう!【最大50%OFF】新春スタートダッシュSALE短答対策編実施中!




 第1回 はじめに
第1回 はじめに
 第2回 財産犯の勉強方法
第2回 財産犯の勉強方法






