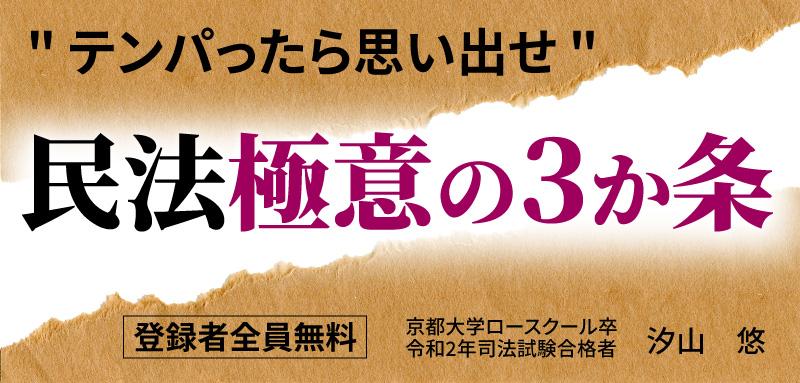
【登録者全員無料】"テンパったら思い出せ"民法極意の3か条
- 登録者全員無料!
京都大学ロースクール生の分析ルールを
テンパったときに思い出そう!
司法試験あるある
初日の選択科目、公法系2科目があまり「パッとしなかった」。だから2日目の民事系科目はなんとかリカバリーしなきゃいけない。
さぁ勝負!民法を開きました!
あれ?理解できない...
自分が思ってる以上にプレッシャーを感じ、うまく問題文が頭に入ってこない...
時間だけが刻々と過ぎていき、焦るばかり...
どんなに勉強をしても本番は緊張するもの!
どんなに真面目に勉強しても、いえ、真面目であればあるほど、本気であればあるほど、試験本番では緊張するものです。
緊張下で問題が頭に入らない場合の対処法を事前に準備しておければ、パフォーマンスを発揮できるのではないでしょうか。
事前準備?それって論証を覚えること?
たしかに論証を覚えることも事前準備として大切ですが、それだけでは本当に問われていることにたどり着くことができないかもしれません。
特に司法試験は、「基本問題が解けるか否か」と「現場でどれだけ問題を分析できるか否か」という出題傾向があるため、「知っている論点にすぐに飛びつくな」などと言われています。
緊張しているからという理由で論証を頼りに答案を書きだしてしまうことは、かえって本当の論点から目を背けることになってしまいます。
何が問われているのかを"分析するルール"を準備しておく
事前準備で重要なことは、現場でテンパったら、緊張して頭が働かないときに頼りにすべき「問題分析のルール」ではないでしょうか。
繰り返しになりますが、司法試験では基本問題+問題分析が重要になります。論証を暗記して準備をするのであれば、問題分析のルールもあらかじめ準備しておいた方が良いのではないでしょうか。
また、問題分析のルールは、答案を書く段階でも有益です。厚く書く部分がわかり、良い意味で"飛ばしていい部分"、"厚く書くべき部分"が自然と現場でわかるというメリットがあります。
- 要件事実で考える=要件事実をそのまま使う
と考えていませんか?
問題分析のルールというは端的に言えば、
・どういう順番で問題を検討するのか
・どの点に着目して掘り下げるのか
・どういう配分で答案を書くのか
などの思考プロセスのルールのことを言います。
ここに決まったルールはなく、人それぞれと言ってしまえばそれまでです。
・ルールが大事なのはわかるが自分が準備できているのかわからない…
・あらためて考えている余裕がない…
こんな悩みのある方のために、BEXAでは、京都大学ロースクール卒業で令和2年度司法試験合格者の汐山悠(しおやまゆう)先生が思考のフレームワークとして問題分析のルール"民法の3か条"を無料で公開いたします。
京大ロー生は一般的に民法への理解度が高い
一般的に京都大学ロースクールで学んだ受験生は(「京大ロー生」といいます。)、民法への理解度が高いと言われています。
もちろん、京大ロー生以外の方でも民法の理解度が高い受験生はいるでしょうけれども、やはり充実した教授陣の講義やハイレベルな同期生に囲まれた環境は、民法の理解度を進めるきっかけになるのでしょう。
民法の問題分析のルール=要件事実的発想での視点の段階化
よく民法は「要件事実的に考えよう」と言われます。
でも、要件事実的に考える=要件事実でそのまま考える、要件事実で答案を書くと考えていませんか?
しかし、実際に試してみると、「要件事実で考え、答案を書く」ということを思考プロセスが多い上に、答案ではかなりの量を書かなければなりません。
あくまで民法の処理手順の中に要件事実的な発想を取り入れる程度に留める方が、実はシンプルなのです。
本講座は、民法の思考プロセスを3段階に分け、それぞれの段階に要件事実的発想を取り入れるポイントを解説します。
①状況の把握
②構造の把握
③配分の把握
○事実の整理でテンパったら?
問題文を読んで、どう整理していいのかわからなくなった時の視点、ヒントを提供します。
○論点把握でテンパったら?
当事者の主張を請求原因・抗弁・再抗弁etc...に振り分ける視点、ヒントを提供します。
○答案構成でテンパったら?
問題文から試験委員が点数を振っているであろう"厚く書くべきポイント"を見つける視点、ヒント提供します。
理論だけでなく実践も
総則編のレジュメと音声講義で①~③の視点を学んだ後には、実践編として直近3年分(平成30年~令和2年)の民法の司法試験過去問を解いていただきます。是非、①~③の3か条を用いて答案を検討してみてください!
実践編のレジュメには事案の整理がしやすくなるような工夫をしています。
京大ロー生の視点、思考プロセスを習得して試験現場でテンパったときのセーフティネットを準備しましょう!
受講形式
総論編はMP3ファイル形式での音声ファイルをダウンロードしてご受講いただけます。レジュメもPDFファイルでダウンロードいただけます。
実践編はレジュメ、PDFファイルのみでの提供になります。音声は附属いたしません。
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0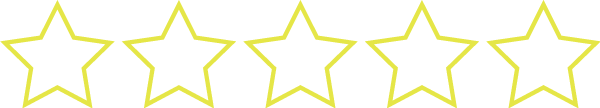
おすすめコメントはありません。




