
予備試験 論文法律実務基礎科目 スピードマスター講義
辰己法律研究所『予備試験論文 法律実務基礎科目 スピードマスター講義』刑事実務基礎
講師推奨プラン
この講座の他のプラン
体験動画・資料
受験界の定番『実務基礎ハンドブック』で一挙に予備論文合格ラインへ!
・今年改訂された『法律実務基礎ハンドブック』最新版講義
・予備試験論文式試験頻出テーマをスピード解説
・元司法研修所教官の監修や予備試験合格者が講義
民訴・刑訴ができれば実務基礎科目ができる!なんて思っていませんか?
──その思い込みが合否を分ける!?
予備試験には、なぜ実務基礎科目があるのか?
予備試験論文試験には、主要7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)と一般教養科目の他に、法律実務基礎科目(民事・刑事)も科目として加わります。
この実務基礎科目、単に科目を増やしたいためにあるわけではありません。
実務基礎で問われるのは、条文知識ではなく“実務家の思考”。
「誰が」「何を」「どう動くか」という現場的な視点を持てるかが、合否を決定づけます。
元々司法修習は1年半~2年ありましたが、その中には「前期修習」というものがあり、前期修習で試験としての民事手続(主に民法・民事訴訟法)や刑事手続(主に刑法・刑事訴訟法)から、実務としての民事手続と刑事手続への視点の切り替えが行われていました。これは「○○があれば、次に××の手続に移行する」というように教科書的なものではなく、より実践的・現場的な視点への切り替えです。
しかし、現行の司法修習制度は1年に短縮されたため、視点の切り替えは法科大学院に移行され、予備試験で実務基礎科目があるのも、その実践的・現場的な視点を持っているか否かを試す意図が実はあります。
独学では到達できない“実務家の思考”を、最短ルートで習得!
実務基礎科目で問われるのは、条文や手続の暗記ではなく、「法をどう使うか」という実務的な視点。
しかし、この“視点の切り替え”は、もともと司法修習で行われていた内容であり、独学で再現するのはほぼ不可能です。
一部の合格者が「民訴・刑訴ができれば十分」と言えるのは、彼らがすでに無意識に実務的思考を身につけているから。
多くの受験生が論文で苦戦する理由は、知識不足ではなく、この視点が抜け落ちていることにあります。
さらに、実務基礎は時間との戦い。
予備試験短答合格から論文試験までの約2か月で、主要7科目と並行して学ぶのは非現実的です。
そこで、受験界の定番である辰已法律研究所『法律実務基礎ハンドブック【新版】』に完全対応した本講座。
実務家の思考を整理したハンドブックの精度と、元司法研修所教官らによる講義のわかりやすさで、
最短時間で「教科書の知識」から「合格答案を生む実務感覚」へ変換します。
効率重視の受験戦略をとるなら──
独学よりも、体系化された講義で“視点の切り替え”を一気に身につけること。それが、最短で合格に近づく唯一の方法です。
講義コンセプト
◆予備試験 法律実務基礎科目対策:合格への最短ルート!
予備試験の論文式試験における法律実務基礎科目は、短答式試験にはない上に、民事と刑事を合わせて試験時間3時間、配点100点と、その重要性は非常に高く、合否の鍵を握る科目です。
短答式試験終了後、いかに効率的にこの科目を攻略し、論文合格ラインに到達するかが極めて重要となります。
◆辰已の法律実務基礎科目ハンドブックの講義の強み!
辰已法律研究所は、長年にわたり予備試験の法律実務基礎科目対策をリードしてきました。
「法律実務基礎科目ハンドブック」:平成23年の初回予備試験開始以来、定番の対策書として多くの受験生が支持する教材!
o刑事は、初版から元司法研修所教官の新庄健二先生が監修。
o民事は、今回の改訂で予備試験・司法試験上位合格者の清武宗一郎先生が監修。
実務経験者だから語れる──“現場の思考”がわかる講義こそ最短ルート
法律実務基礎科目は、その名のとおり実務的な要素が非常に強い科目です。
条文や理論を暗記するだけでは点が伸びず、実際の手続や判断の流れを理解して初めて、合格答案を書けるようになります。
本講座では、元司法研修所教官・元東京高検検事など、実務経験豊富な講師陣が、現場での思考や判断の根拠をわかりやすく解説。
「なぜその手続になるのか」「どのように書面を構成するのか」を、実務家の視点から理解できるため、
独学よりも圧倒的に早く、論文合格ラインへと到達できます。
さらに近年の予備試験論文式試験では、法律基本科目との出題内容の接近現象が見られます。
そのため、法律実務基礎科目の学習は単なる科目対策にとどまらず、民訴・刑訴など主要7科目の理解を深め、得点力向上にも直結します。
◆本講義で一気に合格レベルへ!
本講義では、最新版「法律実務基礎科目ハンドブック」をテキストに、予備試験論文式試験の頻出テーマを徹底解説します。
•刑事:同書の監修者である新庄健二先生が10時間でスピード解説。
•民事:予備試験合格者で辰已専任講師・弁護士の松永健一先生が10時間でスピード解説。
■担当講師

【刑事実務基礎】
新庄 健二 先生
元明治大学法科大学院特任教授。慶應義塾大学法学部卒。社会の耳目を集めたオウム事件の捜査をはじめ検察実務の最前線で活躍される一方、刑事実務教育にも携わり、実務と法曹教育の双方に通暁している。

【民事実務基礎】
松永 健一 先生
東京大学法学部出身。 法科大学院既修者コース在学中に予備試験合格、2015年司法試験合格(上位10%以内)。 説得力ある指導ノウハウが好評。「指導方針が明確」「話がわかりやすい」と人気の先生です。
新庄先生は、伊藤たける講師の『法律実務基礎科目』講義のベースになった先生!
実は、伊藤たける講師も新庄健二先生の講義を受講しています。それまで、教科書的に学習していた刑法などが、新庄先生の講義の受講後は実務的な視点を習得することができたとおっしゃっています。視点を切り替える意識で受講すれば、10時間で、刑事実務で何が求められているのかを深く理解することが可能になります!
◆伊藤たけるのおすすめポイント

■使用教材
■受講形式
インターネット環境下での動画ストリーミング配信によりご受講いただけます。『司法試験予備試験 法律実務基礎科目ハンドブック1&2[第6版]』 をご購入の上、講義をご受講ください。
『司法試験予備試験 法律実務基礎科目ハンドブック1&2[第6版]』 (辰已法律研究所)
▶URL:https://tatsumionline.stores.jp/items/6819637eb7ac336ab229d020
※本講座には附属していませんので、別途お買い求めください
※配布資料はございませんので、ご了承ください
■通常販売価格
・民事/刑事実務基礎セット:65,300円(税込)
・民事実務基礎:34,400円(税込)
・刑事実務基礎:34,400円(税込)
カリキュラム
-
辰己法律研究所『予備試験論文 法律実務基礎科目 スピードマスター講義』刑事実務基礎 プランのカリキュラム
講義時間: 約9時間50分
配信状況: 全講義配信中辰己法律研究所『予備試験 論文法律実務基礎科目 スピードマスター講義』刑事実務基礎
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回第10回第11回第12回第13回第14回第15回第16回第17回第18回第19回第20回
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0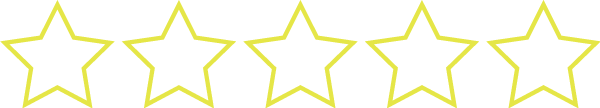
おすすめコメントはありません。




 民事実務基礎
民事実務基礎
 刑事実務基礎
刑事実務基礎



