
SALE 4月13日まで商法・司法試験構造論―司法試験過去問完全対策【H23〜R6答案例付き】
豊田大将『商法・司法試験構造論―司法試験過去問完全対策【H23〜R6答案例つき】』
体験動画・資料
本講座のコンセプト

○過去問分析から得られる感覚的な情報を構造論として提供
論文試験ではあなたの法律知識のほかに、問題を解き・表現する能力が求められますが、これには一種の慣れが必要になります。しかし、この慣れを感覚的に鍛えようとすると方向性を間違えたり、時間がかかったりしてしまいます。
加えて、司法試験本試験の論文試験は基礎知識が出題されるだけでなく、+αで「教科書事例からのズラし」を入れてくる傾向にあります。この「教科書事例からのズラし」に対しても分析し、慣れておくことが必要になります。
本講座は、司法試験本試験の過去問分析から得られる出題傾向・思考プロセス・表現の相場観などの情報を感覚的ではなく構造的に理解することを目的とした講座です。
まだ過去問分析が済んでいない人であれば一気に過去問分析を完了し「教科書事例からのズラし」対策もできます。それだけでなく、これら知識を覚える段階の方であっても論文試験で求められる知識の範囲や意識すべき論点を知ることが可能になります。
【特徴①】出題パターンごとの対策や視点の解説
■商法には出題パターンがある
本講座では平成23年~令和6年の司法試験本試験過去問を豊田大将先生が分析、何が問われているかではなく「どのように問われているか」という視点から出題パターンを導き出しました。本講座を受講すれば、出題パターンごとに何に力を配分すべきなのかが明確になります。
(1)条文検索パターン
主要条文・重要条文を発信元としつつも、その周辺条文(手続)を問うパターンです。
条文を読み込んでいない受験生を混乱させ、条文検索で試験時間を消費させるようなパターンです。
(2)論点抽出パターン
ある規制・ある制度・ある請求根拠が一見問題になりそうだけれども、実は別の規制・制度・請求根拠が問題になっているパターンです。法律論でズラしを入れてくるパターンで、論証しか覚えていない受験生や基本書だけ読み込んでいる受験生に勘違いを起こさせることが狙いのパターンです。
(3)あてはめパターン
典型論点を捻り、具体的な事案に即した検討を求めるパターンです。基本書事例を事実面でズラしてくるパターンで、基本書の読み込みだけでは対応が難しく特に問題慣れが求められるパターンです。たとえば、株主総会での微妙な事実が説明義務違反に該当するかを検討させるようなケースがこのパターンに当たります。
■パターン別出題年度まとめて横断的な把握も可能
さらに、各年度各設問でパターンを抽出するだけでなく、付録でパターン別の出題年度まとめも付けています。この付録によって類似パターンの問題を横断的に把握することが可能です。
【特徴②】思考プロセスの言語化
論文試験ではすべてを書くことは時間制限的に難しく、より配点が多いであろう箇所に集中して厚く論じる必要があります。
本講座では、どのような法律論を用いどの事実をひっぱってくるのかといった答案に組み込むパーツを並べる答案構成を「思考プロセス」と定義します。各年度・各設問に必要なパーツをメモランダム形式で提示し合格者が実際にどういった構成をしているのかを解説。問題文から答案構成までの流れを可能な限り言語化します。
■思考プロセスを準備しておくことでリメイク問題にも対応できる
思考プロセスを学ぶことは初見の問題を考えるための訓練になると同時に、過去に出題されたリメイク問題が再度出題されたときの対応力も鍛えることが可能です。思考時間の短縮、過去問との違いからの特殊性の発見などアドバンテージを得ることができます。
以下では過去に出題されたリメイク問題の例を掲載します。ここに記載されていない問題であっても、来年以降新たにリメイクされる問題もあるかもしれません。



【特徴③】現実的な答案例の提供
パターンや思考プロセスだけでなく、論文試験では答案作成能力も必要になります。しかし、再現答案集などの答案では一部現場で本当に書いたのか疑問が残るものも含まれています。実際の試験現場の緊張・時間制限の下ではよく書けていても6ページ程度が限界でしょう。
本講座では豊田先生が自ら作成した現実答案例が各年度に付属します。ほとんどの答案を意識的に6ページに収めるよう工夫がされており、より現実的なラインでレベル設定がされています。
答案作成能力に自信がなくとも、答案例から問題提起・規範・あてはめのバランスや表現力を学ぶことが可能です。
○こんな方におすすめ
・先に知識をインプットしてからと考えている方
⇒ただ基本書に書いていることを覚えたとしても、試験での「問い」に気付くことができなければ点数は獲れません。あらかじめ商法論文試験の構造を把握し、どういう部分が問われているのかを理解してインプットすることで、基本書を読む際の力の入れどころがわかり、効率的にインプットする助けになります。
・過去問分析の手がかりがわからない方・過去問分析をする余裕がない方
⇒本講座は過去問分析を専門講師があなたの代わりに行い、その情報を提供するものです。「過去問の重要性はわかっている、でも自分の分析に自信がない」「過去問分析の指標がほしい」「まとまった分析結果がほしい」という方にオススメです。
■【令和6年】講義動画を体感!
雑感編
事例検討編
設問検討編
〇受講条件

・講座形式
・通常販売価格
25,800円(税込)
カリキュラム
-
豊田大将『商法・司法試験構造論―司法試験過去問完全対策【H23〜R6答案例つき】』 プランのカリキュラム
- 講義時間: 約15時間42分
- 配信状況: 全講義配信中
豊田大将『商法・司法試験構造論』 講座数 42 15時間42分
-
平成23年①:雑感編15分
-
平成23年②:事例検討編15分
-
平成23年③:設問検討編19分
-
平成24年①:雑感編6分
-
平成24年②:事例検討編24分
-
平成24年③:設問検討編41分
-
平成25年①:雑感編6分
-
平成25年②:事例検討編19分
-
平成25年③:設問検討編30分
-
平成26年①:雑感編6分
-
平成26年②:事例検討編18分
-
平成26年③:設問検討編31分
-
平成27年①:雑感編10分
-
平成27年②:事例検討編19分
-
平成27年③:設問検討編45分
-
平成28年①:雑感編8分
-
平成28年②:事例検討編21分
-
平成28年③:設問検討編45分
-
平成29年①:雑感編8分
-
平成29年②:事例検討編26分
-
平成29年③:設問検討編33分
-
平成30年①:雑感編9分
-
平成30年②:事例検討編27分
-
平成30年③:設問検討編55分
-
令和元年①:雑感編8分
-
令和元年②:事例検討編27分
-
令和元年③:設問検討編38分
-
令和2年①:雑感編5分
-
令和2年②:事例検討編23分
-
令和2年③:設問検討編39分
-
令和3年①:雑感編5分
-
令和3年②:事例検討編25分
-
令和3年③:設問検討編36分
-
令和4年①:雑感編4分
-
令和4年②:事例検討編23分
-
令和4年③:設問検討編38分
-
令和5年①:雑感編6分
-
令和5年②:事例検討編20分
-
令和5年③:設問検討編45分
-
令和6年①:雑感編6分
-
令和6年②:事例検討編22分
-
令和6年③:設問検討編36分
講義を閉じる
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0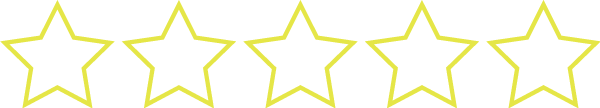
おすすめコメントはありません。
講座に悩んだら

【最大70%OFF!】BEXA SPRING SALE
【最大70%OFF】BEXAに春がやってきた!BEXA SPRING SALEスタート!短答対策講座・条文マーキング講座などがフラッシュセールでお得!




 サンプル
サンプル



