
SALE 4月13日まで苦手なまま受かる!憲法論文フレームワーク講座──厳選過去問16問で予備試験合格ラインに届く
苦手なまま受かる!憲法論文フレームワーク講座──厳選過去問16問で予備試験合格ラインに届く
フレームワークと過去問演習を一体化──憲法が苦手でも、合格ラインに届く講座です。
好評ポイントをPICKUP!
知識と答案をつなぐ論証集─論点想起シート
「知ってるのに書けない」を変える──
論点想起シートは、覚えた知識を3ステップ答案(後述)に沿って整理した論証集です。
ステップ×権利ごとに、どの知識を・どう書けばいいかが明確になるので、論証の使いどころに迷いません。
使い方は動画でご覧ください。
論点想起シートの使い方
講座ガイダンス
憲法で行き詰まっている人へ
「当てはめが薄い」「判例を踏まえろ」──そう言われても、何をどう書けばいいのか分からない。
論点も知っている。判例も覚えた。なのに、答案になると手が止まる。
教材も学習法も一通り試した。けれど、憲法だけは手応えがない。
高得点でなくていい。ただ、合格ラインに届くための具体的な方法が知りたい。
この悩みに、はっきりとした道筋を示すのがこの講座の役目です。
講座のコンセプト
①知識と答案をつなぐ──3ステップアプローチで「苦手なまま」でも合格できる
憲法は、事例が独特で判例との類似性が薄く、覚えた知識をそのまま使えない科目です。
だから、多くの受験生が「知識はあるのに書けない」という壁にぶつかります。
この講座では、その壁を超えるために──
知識を答案に落とし込む“3ステップアプローチ”を提供します。
これは──
・答案の型(構成・分量の整った書き方)
・覚えるべき知識(論点・判例)
・その引き出し方と使い方(論点想起シートと着眼点)
をすべて一体化した、憲法論文の総合フレームワークです。
これに沿って、“当たり前のこと”を丁寧に積み上げればいい。応用力やセンスは不要。
苦手なままでも、合格ラインに届く答案が書けるようになります。
②沈まない答案で戦う──憲法論文の合理的戦略
憲法は、知識だけでなく、その使い方や論述にも配点が大きく、問題によって点数のブレが出やすい科目です。
だからこそ、憲法は上位答案ではなく、安定して合格ラインを超える、いわゆる「沈まない答案」を目指すのが最も合理的です。
基本論点を押さえ、当てはめを丁寧に書ければ、合格ラインには安定して届く。
他の受験生が書けるところを落とさない──それだけで戦えます。
だからこの講座では──
・過去問で重要論点だけを対策
・判例・学説も、答案で使う部分だけ
・マイナー論点は深入りせず、短答知識で対応
やるべきことを絞るから、誰でも再現できる。
それが「沈まない答案」という、憲法における最も合理的な戦略です。
③合格ラインに届く講座設計──フレームワークと厳選過去問で完結
この講座では、憲法論文に必要な「書き方」と「重要問題」の両方を一つにまとめています。
知識を答案に落とし込むためのフレームワーク──型、論点、判例の使い方を整理した3ステップアプローチ。
それを実践的に身につけるため、予備試験の過去問を中心に、司法試験から重要論点を補った16問を厳選しました。
書き方と問題の両面から、合格ラインに達するための最短ルートを提示する──それが本講座の設計思想です。
講座ガイダンス
第1回 R2予 STEP1
第1回 R2予 STEP2
第1回 R2予 STEP3
知識と答案をつなぐ──3ステップアプローチとは
●3ステップアプローチの概要
憲法論文の具体的なつまずきは、主に次の2つです。
・覚えた判例や学説の知識が使えない
・当てはめが具体的に書けない
この2つの“つまずき”を克服するために──
論文の型・知識・思考の視点をすべて組み込んだ、総合フレームワークとして3ステップアプローチを提示します。
「どこで、何を、どう書くか」が明確になり、迷わず答案を書けるようになります。
●3ステップアプローチの4つのポイント
この3ステップアプローチは、以下の4つのポイントから成り立っています:
1. 分量と構成を整える「3ステップ答案」
2.「判断枠組みとしての判例」の使い方
3.「パーツとしての判例」の使い方
4. 書き方に迷わなくなる「着眼点」

ポイント① 分量を整える3ステップ答案
3ステップアプローチの出発点は、「どんな問題でも同じ型で書ける」ようにすること。
そのために、まずは答案全体の構成を3つのステップに整理します。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| ステップ1 憲法問題との抵触 | どの権利がどのように制約されているのか? |
| ステップ2 基準の設定 | どの基準で判断すればよいか? |
| ステップ3 当てはめ | 事案に即して具体的に評価し、結論へと導く。 |
これは、一般的な三段階審査(保護領域 → 制約 → 正当化)を論文用に再配置したものです(下図参照)。
基準ばかり長く、当てはめが短い──あるいはその逆。そんなバランスの崩れは、正しく書けていないことのサインです。
3ステップに沿って書けば、どこにどれだけ書くかが明確になり、構成が安定します。

そしてこの3ステップは、単なる構成のための枠組みにとどまりません。
このあと説明する判例の使い方や着眼点も、すべてこのステップに紐づいています。
ポイント② 判断枠組みとしての判例の使い方──覚えるべき判例はわずか10個
憲法判例の知識を正しく使うには、「2つの使い方」を区別することが大切です。
1つ目は、ステップ2(基準設定)で使う判例です。
いわゆる「判断枠組みとして使う判例」で、基準を立てる場面で、そのまま引用できる形式になっています。
ただし、憲法判例の多くは比較衡量型で、こうした使い方ができる判例はごく一部に限られます(下図参照)。
本講座では、過去問で実際に使われてきた判例のうち、“判断枠組み”として機能するものだけを厳選して解説しています。これを落とさなければ、合格答案に必要な水準は十分に満たせます。

ポイント③ パーツとしての判例の使い方──論点想起シートで知識を自在に引き出す
2つ目の使い方は、ステップごとの論証パーツとして判例を使う方法です。
目的手段審査では、判例の判示部分のうち、目的手段審査に関係のある部分(パーツ)を抜き出して使う必要があります。たとえば、取材の自由が保障されているかは、判例(博多駅事件)のうち、取材の自由について判示している部分を抜き出して答案に書くことになります。
パーツとして判例を使う場面は、特定の権利とステップごとに、ある程度決まっています。
例えば、信教の自由なら、ステップ1で「保障の範囲」「宗教団体の定義」、ステップ2で「間接的制約の評価」「保障の主旨」「政教分離違反の判断枠組み」といった具合に、どのステップで、どの知識を使うかが見えてきます。
本講座では、それらを一覧化した論証集=論点想起シートを用意しています。
このシートは、各ステップ・各権利で問われる「クエスチョン」を提示し、講義の中でその「答え」と「引き出し方」を丁寧に解説します。
さらにその答えも、“沈まない答案”に必要な範囲だけに絞って、現実的に覚え切れる量に抑えています。
復習でもこのシートを使えば、知識の整理も引き出し方の訓練も、すべてここで完結します。

ポイント④ 各ステップに必要な着眼点があるから、書き方に迷わない
憲法の論文試験では、「何を書けばいいのか」が見えずに手が止まる場面が少なくありません。
そんなときに役立つのが、各ステップで使う思考の枠組み=着眼点です。
実は、司法試験や予備試験は年度や分野が違っても、共通する思考の枠組みや注意点があります。この講座では、講師・荒井たかふみが過去問を徹底的に分析し、
実際に使える思考の枠組みや注意点だけを厳選して、着眼点として提供しています。
例えば、手段の必要性の検討の際、「より制限的でない手段」が思いつかず、当てはめが具体的に書けないと悩んでいる人が多いと思います。「より制限的でない手段」は、以下の5つの着眼点を使えば、思いつくことができます。
(1).規制の期間を短くできないか
(2).規制の対象を限定できないか
(3).予防的な規制ではなく、事後的な罰則で足りないか
(4).現状の法制度では対応できないか
(5).類似の問題が現実社会でどう扱われているか
こうした着眼点があることで、ゼロから考え込まずに済み、当てはめが具体的に書けるようになります。
できる人が無意識にやっている思考を、誰でも使える形で示したのがこの“着眼点”です。
論点想起シート(論証集)の使い方
予備試験合格ラインに届く厳選過去問16問
●合格に必要な重要問題だけを厳選
「沈まない答案」を書く。
──それは、誰もが解ける問題で、ミスなく確実に点を取るということです。
予備試験・司法試験は相対評価。
つまり、みんなが解ける問題を取りこぼさないことこそ、最優先の戦略になります。
逆に、「誰も書けないようなマイナー論点」に時間を使うのはコスパが悪い。
点差はつかないうえに、対策にかかる手間は重い。
だからこの講座では、合格に本当に必要な問題だけを、絞って対策します。
●選定基準とカリキュラム設計
・予備試験の過去問を中心に構成。出題傾向や形式に慣れながら、重要論点を網羅。
・予備試験未出題の重要論点も、司法試験過去問や補論(第17回)でフォロー。憲法論文に必要な知識をこの講義だけでマスターできる。
・マイナー論点は深入りしない。R4予備試験の回で、短答知識を使った処理方法を習得。
| 回数 | 年度 | 表題 |
|---|---|---|
| 1 | R2予 | 答案作成の基本/取材の自由 |
| 2 | R3予 | 表現の自由 |
| 3 | R1予 | 処分違憲/信教の自由 |
| 4 | H28予 | 表現の自由(応用1) |
| 5 | H23予 | 平等権 |
| 6 | H26予 | 消極的結社の自由 |
| 7 | H25予 | 結社の自由/立候補の自由 |
| 8 | H30予 | 司法権の範囲/名誉毀損表現 |
| 9 | H29予 | 財産権 |
| 10 | R4予 | 最近の予備試験/マイナー論点解説 |
| 11 | H24本 | 政教分離 |
| 12 | H30本 | 知る権利(抜粋) |
| 13 | R1本 | 表現の自由(応用2) |
| 14 | R4本 | 学問の自由(抜粋) |
| 15 | R5本 | 生存権・平等権 |
| 16 | R6本 | 職業選択の自由/営利表現 |
| 17 | - | 補論/過去問講義で扱っていない論点解説 (プライバシー権、集会の自由、外国人の権利など) |
●すべての問題に、講師によるオリジナル答案が付属
教科書的な理想解ではなく、本番で実際に書ける「沈まない答案」をモデルにしているので、自分の答案と比べるだけで、何を直せばいいかが明確になります。
●フレームワーク × 重要問題──合格ラインに届く力は、この講座で身につく
3ステップアプローチで、論文の型・知識・使い方を整理し、16問の過去問で、合格に必要な重要論点を実践的に押さえる。
憲法だけが書けない──その状態を、ここで終わらせるための講座です。
講師インタビュー
Q1 今までの過去問講座とどの点が違うのですか?
しかし、この方法では、「予備試験には出ていないが司法試験ではよく出ている」分野について問題演習ができません。そのため、問題演習を全ての分野でこなすことができず、ムラができてしまいます。
これに対し、本講座では、予備試験対策を軸にしつつ、司法試験で複数回問われている重要分野の過去問も扱うことで、その穴を補う構成としています。
こうした問題に触れておくことで、予備試験で同様の出題があった際に、大きなアドバンテージになります。
Q2 過去問演習だけで、本当に合格点に届きますか?
しかし、限られた時間の中で、基本7科目・選択科目・実務基礎をこなす必要があり、憲法のように知識の使い方で差がつく科目では、演習書を積み上げるのは非効率です。
そのため、本講座では、あえて題材を過去問に絞り、知識の使い方や論述の仕方の説明に重きを置くようにしました。
また、過去に問われなかった分野の判例知識が出題された場合の対処方法も、令和4年予備試験の回でお話ししています。私自身がこの年に受験したので、試験の現場での対処方法をお話ししています。
Q3 本講義で扱う過去問以外はどうすればよいですか?
「補論」を受講した上で、該当年度の過去問の答案構成をしていただければ、当該分野の対策としては十分です。
Q4 統治分野の論文対策はやるべきですか?
基本的に、出題頻度が低いため、統治分野の論文試験用の対策は不要と考えています。短答試験で統治分野の論点や知識の確認をしておけば十分でしょう。
例外的に、司法権の範囲については対策をしておいた方がよいでしょう。この分野では、直近で判例変更がありました(最大判令和2年11月25日、岩沼市議会出席停止事件、R3重判-憲法2)。本講義では、平成30年予備試験の回で、司法権の範囲についての論述の仕方を、判例変更を踏まえて解説しています。
Q5 この講座を受ければ、司法試験の憲法論文も合格点に届きますか?
司法試験は問題文が長いため、分量感には慣れが必要ですが、何問か答案構成をすれば十分対応できます。
本講座は予備試験向けに設計されていますが、憲法の答案に不安がある司法試験受験者にも有効です。
担当講師 荒井たかふみ
社会人から法律を学び始め、未経験から予備試験・司法試験に短期合格。
合格者が無意識にやっている思考の“型”を言語化し、誰でも再現できるように整理。
単なる知識を「書ける力」に変えることで、努力が確実に成果に結びつく講義づくりを大切にしている。

経歴
・民間企業にて営業職を経験
・一橋大学 法科大学院(既修)入学
・令和4年 予備試験 合格(社会人から初学で短期合格)
・令和5年 司法試験 合格(77期司法修習)
担当講師 荒井たかふみ
受講条件
●講義形式
| テキスト | 受講者様にはテキストをPDFで配布します。 ※製本配送はありませんのでご注意ください。 |
|---|---|
| 問題文 | 問題文は法務省の公式サイトから無料でダウンロード可能です。 予備試験/司法試験 |
| 動画講義 | 動画講義 本講座はストリーミング再生による動画講義です。 ※DVD販売は実施いたしません。 |
●テキスト
| 講義テキスト | 答案作成のプロセスを丁寧に解説したメイン教材 |
|---|---|
| 講師答案 | 本番を想定し、現実的に書けることを重視したオリジナル答案 |
| 論点想起シート (論証集) | 必要な知識と引き出すタイミングを一体化した論証集 |
関連記事
カリキュラム
-
苦手なまま受かる!憲法論文フレームワーク講座──厳選過去問16問で予備試験合格ラインに届く プランのカリキュラム
- 講義時間: 約18時間48分
- 配信状況: 全講義配信中
ガイダンス・論証集の使い方 講座数 3 0時間29分
-
ガイダンス22分
-
論証集(論点想起シート)の使い方3分
-
担当講師 荒井誉史4分
講義を閉じる講義動画 講座数 81 18時間19分
-
第01回_R2予_取材の自由_01_講義を受ける心得4分
-
第01回_R2予_取材の自由_02_問題文9分
-
第01回_R2予_取材の自由_03_第1ステップ10分
-
第01回_R2予_取材の自由_04_第2ステップ21分
-
第01回_R2予_取材の自由_05_第3ステップ_目的審査9分
-
第01回_R2予_取材の自由_06_第3ステップ_手段審査17分
-
第02回_R3予_表現の自由_01_問題文8分
-
第02回_R3予_表現の自由_02_規制①第1,2ステップ21分
-
第02回_R3予_表現の自由_03_規制①第3ステップ、規制②19分
-
第03回_R1予_信教の自由_01_問題文8分
-
第03回_R1予_信教の自由_02_ステップ19分
-
第03回_R1予_信教の自由_03_ステップ2,327分
-
第04回_H28予_消極的表現の自由_01_問題文9分
-
第04回_H28予_消極的表現の自由_02_原告の立場_ステップ121分
-
第04回_H28予_消極的表現の自由_03_原告の立場_ステップ2,37分
-
第04回_H28予_消極的表現の自由_04_あなた自身の見解18分
-
第05回_H23予_平等権_01_問題文10分
-
第05回_H23予_平等権_02_平等権についての基本的知識8分
-
第05回_H23予_平等権_03_原告側主張14分
-
第05回_H23予_平等権_04_反論および私見19分
-
第06回_H26予_消極的結社の自由_01_問題文7分
-
第06回_H26予_消極的結社の自由_02_設問114分
-
第06回_H26予_消極的結社の自由_03_設問213分
-
第07回_H25予_結社・立候補の自由_01_問題文6分
-
第07回_H25予_結社・立候補の自由_02_原告側の主張19分
-
第07回_H25予_結社・立候補の自由_03_反論及び私見19分
-
第08回_H30予_司法審査の範囲・議員活動の自由_01_問題文11分
-
第08回_H30予_司法審査の範囲・議員活動の自由_02_司法審査の範囲(説明)21分
-
第08回_H30予_司法審査の範囲・議員活動の自由_03_司法審査の範囲(論述例)9分
-
第08回_H30予_司法審査の範囲・議員活動の自由_04_処分2(議員活動の自由)15分
-
第09回_H29予_財産権_01_問題文10分
-
第09回_H29予_財産権_02_原告主張_29条1項2項違反、第1ステップ16分
-
第09回_H29予_財産権_03_原告主張_29条1項2項違反、第2,3ステップ11分
-
第09回_H29予_財産権_04_原告主張_損失補償5分
-
第09回_H29予_財産権_05_反論と私見16分
-
第10回_R4予_近時の予備試験_01_問題文10分
-
第10回_R4予_近時の予備試験_02_近時の予備試験の傾向解説5分
-
第10回_R4予_近時の予備試験_03_争議行為の禁止15分
-
第10回_R4予_近時の予備試験_04_あおり、そそのかし15分
-
第11回_H24本_政教分離_01_問題文16分
-
第11回_H24本_政教分離_02_設問1_第1,2ステップ(憲法条項との抵触、判断基準)13分
-
第11回_H24本_政教分離_03_設問1_第3ステップ(当てはめ)12分
-
第11回_H24本_政教分離_04_設問222分
-
第12回_H30本_知る権利_01_問題文19分
-
第12回_H30本_知る権利_02_明確性の原則13分
-
第12回_H30本_知る権利_03_青少年16分
-
第12回_H30本_知る権利_04_成人14分
-
第13回_R1本_表現の自由(応用)_01_問題文15分
-
第13回_R1本_表現の自由(応用)_02_立法措置①_第1ステップ(憲法条項との抵触)17分
-
第13回_R1本_表現の自由(応用)_03_立法措置①_第2,3ステップ15分
-
第13回_R1本_表現の自由(応用)_04_立法措置②_説明14分
-
第13回_R1本_表現の自由(応用)_05_立法措置②_論述例21分
-
第14回_R4本_学問の自由_01_問題文23分
-
第14回_R4本_学問の自由_02_設問112分
-
第14回_R4本_学問の自由_03_設問2_第1,2ステップ17分
-
第14回_R4本_学問の自由_04_設問2_第3ステップ20分
-
第15回_R5本_生存権_01_問題文17分
-
第15回_R5本_生存権_02_設問1_争点①判断枠組み20分
-
第15回_R5本_生存権_03_設問1_争点①当てはめ、争点②、争点③17分
-
第15回_R5本_生存権_04_設問2_争点①、②14分
-
第15回_R5本_生存権_05_設問2_争点③11分
-
第16回_R6本_職業選択の自由・営利的表現の自由_01_問題文15分
-
第16回_R6本_職業選択の自由・営利的表現の自由_02_規制①第1,2ステップ21分
-
第16回_R6本_職業選択の自由・営利的表現の自由_03_規制①第3ステップ15分
-
第16回_R6本_職業選択の自由・営利的表現の自由_04_規制②18分
-
第17回_補論_01_補論の目的3分
-
第17回_補論_02_01_包括的基本権_包括的基本権とは6分
-
第17回_補論_02_02_包括的基本権_情報プライバシー15分
-
第17回_補論_02_03_自己決定権、環境権6分
-
第17回_補論_03_01_思想良心の自由_第1ステップ15分
-
第17回_補論_03_02_思想良心の自由_第2ステップ7分
-
第17回_補論_04_01_集会の自由_集会のための施設の利用拒否18分
-
第17回_補論_04_02_集会の自由_集団行動の自由12分
-
第17回_補論_05_居住移転の自由11分
-
第17回_補論_06_婚姻の自由14分
-
第17回_補論_07_01_外国人の権利_外国人の権利の総論、公務就任権10分
-
第17回_補論_07_02_外国人の権利_外国人の入出国11分
-
第17回_補論_08_01_私人間紛争と憲法_契約関係、不法行為13分
-
第17回_補論_08_02_私人間紛争と憲法_団体と個人6分
-
第17回_補論_09_01_統治_統治分野の対策、統治行為論12分
-
第17回_補論_09_02_統治_裁判官の表現活動8分
講義を閉じる
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0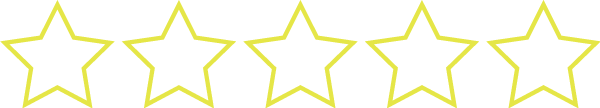
受講者




 4
4
薦められてお試し
これから予備なのでどこまで使いこなせるかはわからないが、今8回目まで受け、過去問はなんとなく解けそう感をもった。
ガイダンス動画をみたときは「慣れてなさそう、大丈夫か?」と思った。講座では雰囲気が違って話し方や教え方もシャープ、オイオイ収録前に撮ったのか?
このガイダンスは損してるんじゃないかと感じたため評価は「ー1」。
受講者




 5
5
「憲法は作文のセンス」ではないことを実感!
これまで、憲法論文は作文・あてはめのセンスだと思い込んできました。
講座をききはじめ、2〜3回まではそのイメージのまま受け進めたのですが、回が進むごとに、
こういうことだったのかという感覚になってきて、答案起案では一番手応えを感じられるのが憲法となるまでになりました。
これまで憲法は焦るばかりで問題を見るのも億劫になっていたのですが、今では憲法がやりたくなってしまうのを切り替えて民事系に集中しています。
同じような気持ちの人は、ダメ元で手に取ってみると案外胃痛の種が和らぐかもしれないです。
受講者




 5
5
論点早期シートと判例の判断枠組みだけでも買う価値はある
丁寧なつくりの講座だし、内容もピンポイントで欲しいつくりだったので講座自体はとても満足している。
特に「論点想起シート」は自分でまとめなきゃと思っていた部分だったので、これが手に入っただけでもとても感謝している。
ありそうで意外となかったのでこれだけでも買う価値はあると思う。
「判例の判断枠組み」という括りの箇所についてもこれだけでも嬉しい2つ目の点。これは他の予備校・講座、択六などではここまで整理されたものはなかったので、これを喜ぶ受験生もたくさんいるのでは。この判断枠組みの整理では、射程の理解を身につけたベテランの頭の中を綺麗に見せてくれたようなイメージでした。よくいわれる「判例の射程」は、1つ1つの判例の判断がどこまで他のケースでつかえてどこからつかえないかというような「1対多」の理解をしていかないといけない構造にはなるので頭がこんがらがるし受験生として1つ1つみていったり、他との矛盾を考えたりと勉強が地道で大変だなあと思っていたところに、これが手に入ったことで一番頭をひねっていたところが解消された気持ちです。
1点だけもったいないのはバニラさんは「しゃべり」はうまくはない。朴訥といった感じで、田舎の先生といった感じ。
口だけ上手くていい加減にやってそうな先生が講師の中ではよくみかけることを考えれば、誠実でいいという人もいるかもしれない。
アガルートのスター某先生も鼻すすり音が異様に気になるというのはよく聞く話、そう思えば業界的にはめずらしくないんでしょうか。
講座に悩んだら

【最大70%OFF!】BEXA SPRING SALE
【最大70%OFF】BEXAに春がやってきた!BEXA SPRING SALEスタート!今週は短答対策講座・条文マーキング講座などがフラッシュセールでお得!
「荒井たかふみ 予備試験合格日記」#1 なぜ法律知識ゼロで弁護士を目指したのか
法律ゼロから予備試験・司法試験短期合格!荒井たかふみ講師の受験体験談をお届けするシリーズ第一弾です!
【全講座7%OFF】Reスタートクーポン!来年の合格に向けて、今日から動くあなたを応援!
「来年こそは」「今日から始めてみよう」と、来年の司法試験合格に向けて動き出すあなたの一歩を後押ししたく、BEXAでは全講座に使える7%OFFクーポンをご用意!
【2025/10/3(金)20:00~】BEXA予備試験合格講師陣が語る R7年予備試験 現実的合格答案大公開!〜行政法編〜
令和7年予備試験の現実的合格答案を、予備試験合格講師である剛力大・荒井誉史講師が徹底解説します! 今回は行政法編!苦手なまま受かる!憲法論文フレームワーク講座──厳選過去問16問で予備試験合格ラインに届く
フレームワークと過去問演習を一体化──憲法が苦手でも、合格ラインに届く講座です。










