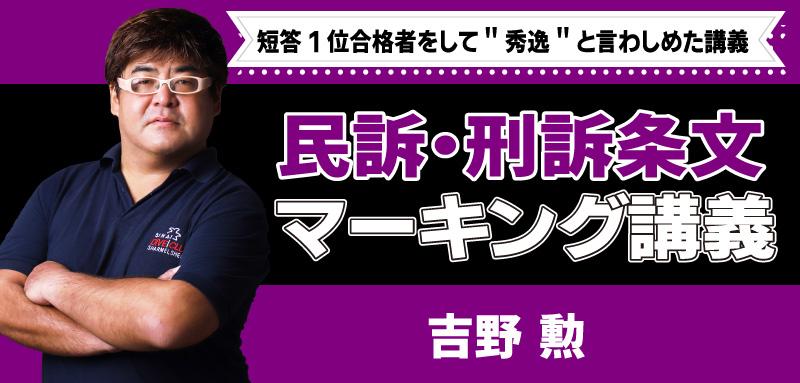条文が読めるようになる! 「未知の問題を解く力」を条文マーキングで磨こう!

「基礎講座は終わった。短答も少しずつ解けるようになってきた。でも、論文になると手が止まる――」そんな経験はありませんか?
その原因は、条文そのものと向き合っていないことにあるかもしれません。
しかし、条文の理解は一朝一夕では身につかないため、多くの受験生が壁にぶつかることが多くあります。
条文学習は「今」始めないと間に合わない!試験まで時間がある今こそ、条文と向き合うとき!
直前期の3月以降に焦って条文学習をはじめても、他にもやるべき学習がありすぎて手が回らず、試験本番を迎える受験生が多いのが現状です。まだ時間があるから大丈夫!と思っていても実は、今始めないと試験に間に合わないのです!
条文学習は地味で時間がかかります。派手な勉強法ではありません。しかし、この地道な積み重ねが、確実な実力につながります。試験本番で「条文をしっかり勉強しておいてよかった」と思える日が必ず来ます!
法律学習の落とし穴!「わかったつもり」の危険性
事例で覚える学習の限界
多くの人は、具体的な事例や判例を通じて法律知識を覚えています。「この事案ではこの論点」「あの判例ではこう判断された」といった形で知識を積み重ねるわけです。しかし、この学習法には大きな落とし穴があります。それは、事例や場面で覚えている人は、想定外の問題に対応できなくなるということです。
基礎講座を受けて問題集を解き、「わかった」と感じても、本番で少し角度を変えた問題が出ると手が止まってしまう。「わかったつもり」の知識は、試験の現場ではバラバラになってしまいます。
一方で、条文から学ぶことで、文言を正確に理解し、具体的な事案にどう適用するかを考える力が養われます。時間はかかりますが、この学び方こそが、どんな事案にも対応できる「応用力」を生み出します。
試験では、見たことのない事例が出題されます。そんな時でも、条文ベースで学んでいる人は、「条文の要件に当てはまるか」を軸に答案を構成できます。条文は、すべての事案に通じる法律学習の地図なのです。
法律学習ができるようになる4つのサイクル
法律学習は、螺旋階段を登るようなものです。同じ場所を何度も通りながら、少しずつ高い場所へ到達していく。一度では完結しない、周回が必要な学習です。
サイクル1:知る
まずは、基礎講座や入門書で、法律の全体像を学びます。民法スピードマスターのような教材を使って、各制度の概要をつかむ段階です。この段階では、「ふんわりとした理解」で構いません。全体像を把握することが目的だからです。
サイクル2:解く
短答問題で知識を確認し、論文問題で応用力を試す。問題を解くことで初めて、自分が何を理解していて、何を理解していないのかが見えてきます。「わかっただけでは解けない」のが法律の世界です。問題が解けない現実とむき合わなければいけない大変な時期ですが、ここで立ち止まってはいけません。
サイクル3:深める
問題を解いて浮かび上がった疑問点を、条文に戻って確認します。判例や学説を参照し、理解を深めていく。「なぜこの条文がここにあるのか?」「この要件の意味は何か?」条文を読み込むことで、法律の構造が見えてきます。
サイクル4:まとめる
学んだ知識を条文に書き込み、整理します。ここでおすすめの学習が条文マーキング講義です。条文マーキング講義を受講することでバラバラだった知識が、条文を軸に一つにつながっていき、問題演習で学んだこと、判例で確認したこと、基礎講座で聞いたこと、それらすべてが、条文という「地図」の上に配置されていくのです。
このサイクルは1回では完結しません。何度も繰り返すことで、知識が定着し、法律全体像が見えてきます。1周目では見えなかったことが、2周目で見えてくる。2周目で疑問に思ったことが、3周目で腑に落ちる。螺旋階段を登るように、少しずつ理解が深まっていくのです。また、同じ教材、同じ条文を繰り返し読むことで、毎回新しい発見があります。「前回はここで止まったけど、今回は先に進める」その積み重ねが、確実な力につながります!
そう思っているあなたにおすすめなのが、吉野勲講師の条文マーキングシリーズです!
吉野勲講師の条文マーキングシリーズの特徴
特徴1:スキマ時間で学習できる!音声学習だから、いつでもどこでも学べる!
- 通勤中の電車の中で
- 家事をしながら
- ちょっとした待ち時間に
あなたに代わって、吉野講師が条文を読み、その内容をわかりやすく解説!。あなたは、講義を聞いているだけでOKです。動画ストリーミング配信のみのプランだけでなく、インターネット環境がない場所でも再生可能な「音声ダウンロードプラン」もご用意しております。
特徴2:メリハリのある学習!
その心配は無用です。BEXAの条文マーキングシリーズは、吉野講師が長年の経験に基づき、出題傾向を分析しています。だから、メリハリをつけて学習ができるのです。
特徴3:合格者も認める品質!
苦手な方でも大丈夫!短答一位合格者から"秀逸である"と言わしめた、吉野勲の講義の良さ、面白さを実感できる内容となっています。
条文マーキングなら条文が読めるようになり、未知の問題を解く力も身につく!今こそ、未来を見据えた学習で合格への一歩を踏み出しましょう!
関連講座
2025年11月27日 吉野勲
役に立った:0