[刑法]共犯者間における抽象的事実の錯誤について質問です。
かかる論点は、どの要件充足性を判断する上で問題となる論点なのでしょうか?
共謀(=特定の犯罪についての意思連絡)が認められるか。という問題なのでしょうか?
だとすれば、共同正犯の要件たる②共謀に基づく実行行為を認定する前に書くこととなってしまい、錯誤であることを述べづらいので困っています。
答案を実際に書く際の視点からご教授願います。
刑法では、体系上の位置づけを常に意識する必要がありますから、大変いいご質問だと思います。
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
以下、②の事案についてです。
(前提として、共謀(=特定の犯罪についての意思連絡及び正犯意思)は、さらっと認定。)
共謀の射程というのは、共謀に「基づく」実行があったと言えるか。という要件についての問題と把握しています。
以上が、共同正犯が成立するか、すなわち、客観的構成要件該当性についての処理。
⭐️その上で、次に(責任)故意が、Yにおいて、どの程度まで認められるか≒共犯がどの範囲で成立するか。というのは、主観的構成要件該当性(もしくは、責任)についての処理。
といった、理解で正しいでしょうか?
(であれば、)⭐️の部分については、シンプルに、単独犯の場合における錯誤と同様に、法定的不合説で処理する場面であり、部分的犯罪共同説について論じる場面ではないのでしょうか?
以下、②の事案についてです。
(前提として、共謀(=特定の犯罪についての意思連絡及び正犯意思)は、さらっと認定。)
共謀の射程というのは、共謀に「基づく」実行があったと言えるか。という要件についての問題と把握しています。
以上が、共同正犯が成立するか、すなわち、客観的構成要件該当性についての処理。
⭐️その上で、次に(責任)故意が、Yにおいて、どの程度まで認められるか≒共犯がどの範囲で成立するか。というのは、主観的構成要件該当性(もしくは、責任)についての処理。
といった、理解で正しいでしょうか?
(であれば、)⭐️の部分については、シンプルに、単独犯の場合における錯誤と同様に、法定的不合説で処理する場面であり、部分的犯罪共同説について論じる場面ではないのでしょうか?
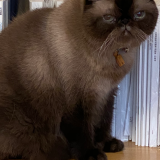
2025年9月15日
加藤洋一
講座講師
ご質問内容に刑法の実力を感じます。
よく勉強されてますね。
さて、まず前段はそのとおりです。
次に☆について回答します。
ここはまさに責任故意の問題です。
したがって、ご指摘どおりの処理でいいのですが、罪名、つまり共犯関係で部分的犯罪共同説が必要になります。
Xには殺人罪の単独犯が成立し、XとYには傷害致死罪の共同正犯がせいりつすることとなるからです。
よく勉強されてますね。
さて、まず前段はそのとおりです。
次に☆について回答します。
ここはまさに責任故意の問題です。
したがって、ご指摘どおりの処理でいいのですが、罪名、つまり共犯関係で部分的犯罪共同説が必要になります。
Xには殺人罪の単独犯が成立し、XとYには傷害致死罪の共同正犯がせいりつすることとなるからです。
2025年9月15日
とても、迅速かつ丁寧にご対応いただき、ありがとうございます!
責任故意が認められる範囲の画定。
↓もっとも、
異なる罪名間で、共犯を成立させても良いのか。といった形で、部分的犯罪共同説を論じる。
という風に処理すれば良いのですね!
責任故意が認められる範囲の画定。
↓もっとも、
異なる罪名間で、共犯を成立させても良いのか。といった形で、部分的犯罪共同説を論じる。
という風に処理すれば良いのですね!

