気になりませんか⁉「CBT方式の司法試験・予備試験」について。BEXA事務局では対策に向けた状況を整理してみました(11/24更新)

|基本情報
法務省は、令和 8 年度(2026年度)実施分から、法曹養成制度における司法試験(および司法試験予備試験)を「CBT(Computer Based Testing:コンピュータ上で答案を作成・提出する方式)」に切り替える予定であることを公表しています。 具体的には、受験会場に備えられた端末(PC)を用いて受験を行い、解答用紙ではなく電子入力・提出方式とする見込みです。
また、CBT方式の操作感を受験生が事前に確認できる「体験版システム」が公開されています。
CBTシステムの体験版はこちらから⇩
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html
[PDF] 司法試験のCBT方式の導入及び出願手続のオンライン化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/content/001437905.pdf
[PDF] 司法試験等CBTシステム 体験版操作マニュアル
https://www.moj.go.jp/content/001437909.pdf?utm_source=chatgpt.com
|予備校各社の取り組み情報
司法試験・予備試験対策において、主要な予備校・通信講座には以下のような動きがあります。
まず、I校は、2026年度以降CBT方式の導入を見据えて「司法試験 CBT答練パック」を開講し、「実際にパソコンで答案を作成・提出する一連の流れを早期に体験することで、受験生が差をつける」ことを主眼に据えています。 また、学習ガイドとして「CBT学習ガイド」も公開し、PC操作やタイピング速度、画面入力の慣れなどを重視しています。
次に、A校は、司法試験・予備試験講座において、「効率重視」のカリキュラムを打ち出しており、CBT化への対応として通信主体・短期間集中型の学習を支持する受験生を取り込んでいます。
さらに、K校は「CBT試験では条文検索のしづらさ・答案構成の難易度が上がる」と指摘し、紙媒体六法からの移行を見据えた「条文記憶重視」対策を打ち出しています。
また、伝統校として、L校やT校も、その長年の実績を活かしつつCBT対応講座・体験版活用の動きを見せています。これら各社はいずれも、従来の手書き試験形式からの移行という受験環境の変化を受けて、早期からPC操作・デジタル答案作成を意識した講座開発を進めています。
|今やるべきは、各予備校の「セールストーク」に乗る前に受験生自身が「CBT環境に慣れる」こと
法務省の体験版を「とにかくいじってみる」「「CBT環境に慣れる」がコスパ・タイパの良い策の一つではないでしょうか⁉
その意味では、以下については『すっ飛ばして』いただいても結構です。「デジタルとアナログの最適な融合点」を探る過渡期でありますのでお読みいただければ、皆さま勉強の一助になると幸いです。
|BEXAの取り組みや評判
BEXAでは、司法試験・予備試験向けに多数のコラム・記事を公開しており、その一部を紹介します。
「AI(ChatGPT)が司法試験答案をどう評価するのかを検証し、人間の思考との違いを浮き彫りに!」という記事では、答案構成・論理展開の観点から、AI時代における“法律脳”の鍛え方を提示しています。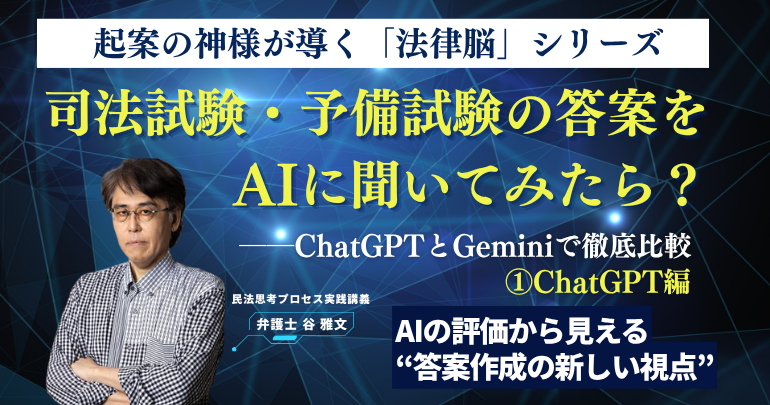
https://bexa.jp/columns/view/1139
また、「条文+問題文」で評価される答案を書く『4Sマル秘訓練法』という記事では、①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめ、という4段構成を軸にアウトプット重視の訓練法を紹介しています。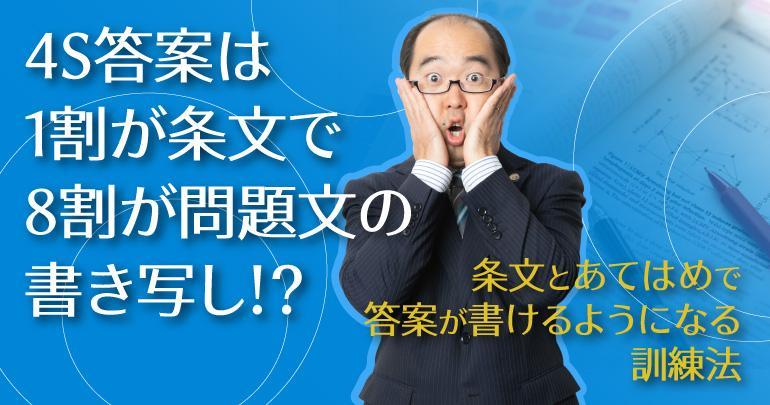
https://bexa.jp/columns/view/1087
さらに、BEXAの講座評判を調べる記事では、「BEXAは“講師と受講生をつなぐ場所”を提供するサービス型」であり、他予備校のような全科目カバー型・手厚いフォロー体制型ではない一方で、「受講生自身が主体的に講座を選び、必要な科目を重点的に学ぶ」スタイルに向いていることが指摘されています。
これらの記事から、BEXAは“精鋭講師・単科講座・アウトプット重視”という方向性を打ち出しており、CBT化という受験環境の変化にも敏感に“答案力とデジタル操作対応力”の両面を意識していることがお分かりいただけると思います。
|CBT試験で大きく変わるポイントとBEXAが役に立つところ
■CBT方式導入による大きな変化
まず、受験環境・形式の変化として、①答案作成手段の変更、②条文・資料参照様式の変更、③時間管理・操作感の変化という三つの大きなポイントがあります。
①答案作成手段の変更
従来は手書きで紙に答案を記述して提出していましたが、CBT方式ではPC・端末上で答案を作成・提出することになります。
手書き特有の筆跡・読みにくさといった採点リスクが軽減される一方、タイピング速度・画面上での解答構成力・誤字・誤入力等、別のスキルが問われるようになります。 また、答案を “書く” という物理的作業から、 “入力・編集・スクロール・検索” というデジタル操作が中心になります。
②条文・資料参照様式の変更
紙の六法や判例集を手元に置いて参照していた方式から、画面上の条文ボックス・検索機能・電子資料参照という形式に変わります。 たとえば、紙媒体の六法に比べて一覧性・俯瞰性が低下するという指摘があります。加えて、条文検索の操作、キーワード入力、スクロール・ウィンドウ切り替えなど、デジタル特有のストレス・時間コストも無視できません。
③時間管理・操作感の変化
PCでの受験では、マウス操作・キーボード入力・画面切替などが答案作成・構成において時間・手間として影響します。
さらに、体験版では「戻るボタンがない」「余白・メモ欄が制限される」などの仕様面での違和感も指摘されています。 このため、従来型以上に「操作の慣れ」「解答構成のスムーズさ」「ミス回避」が得点に直結する可能性があります。
また、制度運営面でも、出願手続きのオンライン化・受験手数料のキャッシュレス化等の流れがあり、デジタル社会化の文脈でこの変更が位置づけられています。
以上のように、ただ“知識を詰める”だけではなく、“デジタル操作対応力”“PC答案構成力”が新たに加わるという点が、今回のCBT化で受験生が備えなければならない大きな変化です。
■BEXAが役に立つところ
そのような変化を踏またうえで、BEXAが受験生にとって有用となるポイントを整理します。
アウトプット重視・答案構成訓練の講座ラインアップ
BEXAでは「4Sマル秘訓練法」など、答案構成(当事者確定→言い分→法的構成→あてはめ)を重視する講座を提供しています。これがCBT方式で問われる“画面上での答案構成力”“要点を明確にパソコンで伝える力”と合致します。既にBEXAが提示する“書くだけではなく構成して伝える”視点が、CBT化後の形式変化に対応した学習設計になっていると言えます。単科・専門講師型講座による重点補強型学習
BEXAは、「講師と受講生をつなぐプラットフォーム」であり、他社のような大規模フルパッケージではなく、受験生自身が「苦手科目を集中的に」「得意科目をさらに上積み」できる講座を選べる構造です。
CBT化により「操作に慣れる時間の確保」「答案構成訓練量の確保」がより重要になるため、全科目を広く浅くではなく、自分の弱点/新形式対応部分を掘り下げるBEXAのスタイルは非常に適しています。デジタル対応・学習ガイドの提示
BEXAでは、AI/デジタル時代対応をテーマにした記事(「AIが司法試験答案をどう評価するか」等)を公開しており、受験生に対して単なる知識習得ではなく“思考・構成・伝達”という観点の学習が必要だというメッセージを発信しています。これにより、PC上での答案作成・画面入力・構成スキルといった“新たな技能”も意識させる設計になっています。コスト・選択の自由度
口コミ等によれば、BEXAは「安い価格で高品質講座が受けられる」「必要な講座だけを取れる」という評価があります。 CBT化を控えている今、受験生は「従来型+CBT対応」という二重対策を迫られる可能性があります。その際に、最低限必要な“CBT対応講座”をコストを抑えて受講できるという点は、BEXAの大きな強みとなります。
■学習戦略としての提言
CBT方式移行にあたって、受験生として意識すべき戦略は以下のとおりです:
早期に「PC操作・タイピング・画面入力・検索」等の技能を実践的に鍛える
BEXAでも“アウトプット訓練・答案構成講座”を活用し、パソコン上での答案作成を想定した演習を行うことが効果的です。
条文検索/資料参照の効率を高める
「紙の六法依存」から“条文本体の記憶+画面検索スキル”へ移行が必要です。BEXAの論文構成・答案訓練講座を併用し、条文知識をアウトプット中心で定着させると良いでしょう。
時間配分・操作ミスを想定した訓練を重ねる
CBTでは誤入力・操作ミス・画面切替ロスなどが点数差を生みうるため、模擬演習を通じてその種の“落とし穴”を潰していく必要があります。BEXAの講座でアウトプット量を確保しつつ、模擬PC環境での演習を組むことを推奨します。
自己分析・弱点補強を重点的に
従来型からCBT型への移行により、どの科目/どの論点/どの操作で時間を浪費しやすいかを見極め、その部分をBEXA等で補強する戦略が有効です。
形式変更を「機会」と捉える
CBT化は受験生全体にとって新しい環境であるため、操作・形式に慣れていること自体がアドバンテージになりえます。BEXAで早めに対応を進め、ほかの受験生より先に“操作慣れ+構成力”を備えておくことが勝機となります。
“答案力とデジタル操作対応力”UPに推奨
2025年10月26日 BEXA事務局
役に立った:2






