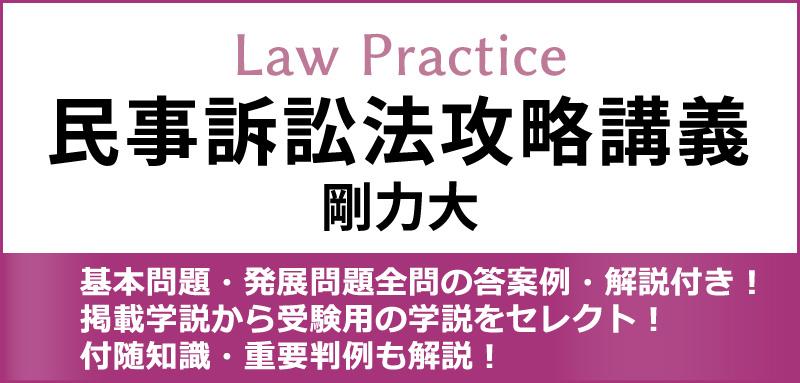司法試験 合格体験記2024「教材を減らしたら、成績が伸びた」3回目で掴んだ逆転合格の一手

「やるほどに不安が増える」完璧主義が生んだ学習の悪循環
ロースクールに入学してから、私はずっと「自分だけが遅れているのではないか」という不安を抱えていました。
片道2時間の通学、毎朝8時半からの授業。予習で手一杯で、復習や思考の整理までは手が回らず、学習の積み重ねができていない感覚があったのです。
私はもともと不安症で完璧主義な性格です。授業で当てられて答えられなかったらどうしようという気持ちから、必要以上に調べてしまう癖がありました。
課題も、周囲がさらっと出す中で「この論点で合っているのか」「もっと調べたほうがいいのでは」と、基本書やデータベースまで確認して提出していました。「みんながこれくらいやっているんだろう」と思い込んで、手持ちの教材以上の情報にまで手を広げていたのだと思います。必要のない情報まで取り込もうとして論点がぼやけ、かえって時間ばかりが過ぎていきました。
答案でも、「この順番でいいのか?」「この事実を拾い忘れていないか?」と考えすぎてしまい、構成にメリハリのない、詰め込み型の答案になっていたと思います。
友人たちが淡々と演習を進めているように見える中、自分だけが取り残されているような気がして、安心材料として教材をどんどん増やしていました。でも、調べることや教材に頼ることでしか不安を埋められず、知識の整理もできないまま、不安だけが大きくなっていくばかり。
そんな状態で司法試験の1回目を迎えることになります。
「勉強量」を増やしたのに司法試験2回不合格
憲法については、直前期にずっと使っていたテキストとノートを読み返しただけで、他の科目ほど時間をかけたわけではありません。それでもAが取れたことで、「必要な部分を押さえれば、それだけで点が入ってくるんだな」という手応えは確かにありました。
ですがそのときは、本質的に勉強のやり方を見直すには至りませんでした。
むしろ、「勉強時間が足りなかったからだ」「もっと教材をやり込まなければ」と考えてしまい、2回目の受験では“とにかく量を増やす”という方向に進んでしまいました。
しかし、結果は不合格。1回目よりも総合得点は大きく伸び、たとえば刑法ではA評価を取ることができたものの、それでも合格には届きませんでした。
頑張った実感があったからこそ、結果を見たときのショックは大きく、「これだけ勉強してもダメなのか」と心の底から落ち込みました。
そのとき、ようやくはっきりと自覚したのです。「やり方そのものが間違っていたのだ」と。
努力の“量”だけでは合格できない。むしろ、自分にとって必要なことに絞り込み、“やるべきこと”を正確に選ぶことができていなかった。その認識が、次の一手を考える出発点になりました。
そこで、11月下旬に入るまでの約1ヶ月間は、いったん手を止めて、勉強法や自分の成績をノートに整理する時間にあてました。
このとき振り返って気づいたのは、たとえば以下のような点です。
勉強法で「間違っていた」と気付いたところ
答案を書く練習の際、分析本のA評価からE評価まで全ての答案を読んでいた。
・実際は、A答案の良いところと悪い答案の悪いところだけ見れば十分だった。
・いろんな答案を全部読むのは時間の使い方が悪かったと反省した。
・時間的余裕があり低い評価の答案を読むことができるとしても、その答案の改善ポイントをおさえるだけにすればよいと分かった。
合格者の再現答案には脚色が入っているのに気づかず、過信しすぎていた。
・「ここまで書かなきゃいけないんだ」と思ってしまい、余計な知識まで覚えようとしていた。
・論証集でも、細かすぎる部分まで気にして、暗記の効率が悪くなっていた。
A答案の書き方や順番が違うだけで、「これが正解」と思い込みすぎていた。
・どの問題にも共通する書き方を探しすぎて、時間を取られていた。
・「こういう書き方もあるんだ」と割り切ればよかったのに、それができなかった。
分析本を読んだり講師の解説を見て、腑に落ちなかった時にすぐ基本書に戻っていた。
・その結果、理解よりも知識に寄りすぎていた。実際に書く練習の時間が減ってしまった。
こうした反省を踏まえ、「もう一度同じやり方をしても絶対に受からない」と感じた私は、自分の目的に合った勉強の方向性を再構築する必要があると考えるようになりました。 ちょうどその頃、BEXAの決起集会に参加し、自分のノートにまとめた「成績の変遷」「今までの勉強法」「これからの戦略」などを持って先生方からアドバイスを受けました。 信頼できる人に自分から相談するように意識を変えたことも、大きな転換点になりました。
思い切って「教材を減らす」ことが1番の戦略だった
これまで私は、「不安だから」「念のため」と、各科目に複数の基本書や演習書を並べて使っていました。しかし振り返ってみると、それは情報や選択肢が多すぎて、かえって判断を鈍らせていたように思います。
そこで3回目の受験では、思い切って教材を“物理的に減らす”ことから始めました。
基本書は原則1冊まで。演習書も、今の自分に必要だと判断できるものだけに絞り、それ以外は箱にしまって視界からも消しました。手元にある教材を最小限にすることで、「今やるべきこと」に集中できるようになったのです。
教材の絞り込み方と使用法
憲法・知的財産法
・得意科目のため、演習書は使わず、過去問のみで対応。知的財産法は1週間で17〜18年分の過去問を分析。うち5年分は実際に答案作成し、残りは答案構成のみ。出題趣旨・採点実感も確認しながら、論証集の暗記は5月までに完了していました。
民法・商法・民訴(民事系3科目)
・BEXAのLawPractice講義を活用し、教材はLawPractice1冊のみ。あとは令和の5年分の過去問を起案し、それ以外は答案構成するだけでした。
刑法
・過去問と『刑法事例演習教材』を併用。過去問の問われ方に慣れておきたかったので、過去問を優先。
刑訴
・『エクササイズ刑訴法』と過去問を中心に、必要に応じて『リーガルクエスト刑事訴訟法』と判例集で丁寧に補強。
行政法
・『基礎演習行政法』と『実践演習行政法』を併用し、過去問の復習時に『行政法憲法ガール』を使って理解を深めました。
全科目共通で、原則1科目1冊+過去問という方針で教材を絞りました。例外は、苦手だった刑訴と行政法で、それぞれ3冊ほど使いましたが、それでも全体的な教材の総量は2回目までとは比べものにならないほど減りました。
BEXAのLawPractice解説講義がもたらした変化
この教材の絞り込み戦略を進める上で、特に大きな意味を持ったのがLawPractice講義でした。
剛力先生は高校・大学時代の同級生だったこともあり、BEXAのYouTubeの配信を見て勉強法を知り、「民事系はこの先生方でやってみよう」と思い、受講を決めました。
講義を受けたことで、三段論法の“上の部分”=問題提起・理由づけ・規範定立について「このくらいでいいんだ」と納得することができ、暗記の方法や論証の定立の仕方に対する戦略が立てやすくなりました。
三段論法の精度を上げようとは思っていなかったが、簡潔さやメリハリを意識する中で、結果的に精度も副産物的に上がったと思います。
各先生の講義内容と自分の受講の意義は、以下の通りです。
剛力大「LawPractice民事訴訟法攻略講義」
・問題提起・理由づけ・規範定立を端的に示してくれた。
・「三段論法の上の部分はこのくらいでいいんだ」という基準が得られた。
葵千秋「LawPractice民法攻略講義」
・民法は量が多く、モチベーションが落ちやすいが、解くべき問題数が決まっており、取捨選択しやすかった。
・改正法対応の参考答案があったのもありがたく、「やる・やらない」の指針が明確だった。
望月楓太郎「LawPractice商法攻略講義」
・商法は好きではなかったが、「これだけ覚えればいい」いう指針を示してくれたことで心理的ハードルが下がった。
・苦手科目で暗記量を減らせることがわかり、取り組みやすくなった。
総じてLawPractice講義は、得意科目でさらに得点を伸ばすというよりも、苦手科目で「不合格答案を書かない」ための最低ラインを確保するのに最適でした。
民事系が苦手だと思っていた私にとって、自分だけで進めるよりも、的確な方向性を示してもらえる講義の存在は大きかったです。
合格をつかんだ3回目!合格答案を書ける準備を続けた
司法試験受験の3回目は、合格に向けて教材を絞り、「確実に合格答案を書ける状態をつくること」を最優先に勉強を進めていきました。
勉強のスケジュールも、「暗記時間を確保しながら、過去問ベースで不安な部分を潰していく」ことに集中しました。
学習スケジュールと方針
年内(〜12月)
・択一中心。
・朝8時〜15時までは択一問題を解く時間にあて、空いた時間には『趣旨規範ハンドブック』で全科目の論証集をインプット。
・余力がある日はロープラクティスを解いたり、講義を視聴。
年明け〜春(1月〜4月)
・論文中心に切り替え、特に民事系からスタート。
・刑事系や公法系は、民事の流れが落ち着いてから段階的に進めた。
・択一も継続的に演習し、短答知識の確認を並行。
直前期(5月〜7月)
・短答と論文を5:5の比率で並行学習。
・論文は暗記と答案構成を重視。
直前期の1週間の過ごし方
民事系(民法・商法・民訴)
・1日目:朝から民法、昼までに過去問→復習。午後は商法の過去問を解いて復習、18時まで暗記。夜は不安な部分をテキストで確認。
・2日目:民訴を解いて復習、午後は前2日間の不安箇所を再確認し、基礎事項や刑事系論証集も確認。
刑事系(刑法・刑訴)
・刑訴に不安があったため、1日目は1時間あたり1問「エクササイズ刑事訴訟法」を確認し、わからない部分は論証集やリーガルクエストで補完。理解の時間を優先して確保。
・1週間ほどは刑訴に集中し、過去問演習と復習を繰り返す。
・刑法は、過去問中心で繰り返し演習。
公法系(憲法・行政法)
・行政法は過去問演習を通じて考え方の復習をしつつ、テキストを読み込んで知識整理。
・憲法は、行政法と同時に過去問を並行して演習。
選択科目(知的財産法)
・1週間で過去問17〜18年分を消化。うち5年分は実際に答案作成。残りは答案構成。
・出題趣旨・採点実感を確認。
・5月中に論証集の暗記を完了させた。
3回目の本試験結果
努力の方向性を見直し、戦略的に教材と時間を絞った結果、以下のような評価を得ることができました。
| 科目 | 憲法 | 民法 | 刑法 | 民訴 | 刑訴 | 商法 | 行政法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | B | A | B | B | A | D | D |
順位は前回より約700番上昇し、1400位台で合格となりました。
苦手な科目で「不合格答案を書かない」レベルを確保し、得意科目で確実に点を積み上げる──
この方針をとって初めて、形になったと感じた試験でした。
自分の限界を正しく見極め、やるべきことを絞ったからこそ得られた合格だったと思います
受験生へのアドバイス──計画的な戦略と積極性が合格へ繋がる
①計画を立てて、自分に合った勉強法を見つける
私から受験生の皆さんに伝えたいことは、「ただ頑張る」だけではなく、どこに向かってどう頑張るかを明確にすることが大切だということです。
とくに複数回受験している方は、目指す順位や取るべき評価を最初に決めておくべきだと思います。
たとえば私の場合、「どの科目でも不合格にならない答案を書くこと」「満遍なくAかB評価を取りたい」という目標がありました。目的が定まれば、その中で戦術的な勉強法を考えやすくなります。
世の中にはいろいろな勉強法がありますが、それらはあくまで「パーツ」にすぎません。今の自分の状況に合ったものを見極め、取捨選択する力が必要です。
だからこそ、試験日から逆算して、全体の計画(戦略)を立てたうえで、教材や学習法(戦術)を選んでいくことが大切だと思います。
また、勉強を淡々とこなすことの中にも、ちょっとした工夫や楽しさを見出すことが、継続のカギだと感じています。
暗記の時間も、内容ではなく「今日は何問覚えた」「10分でも進んだ」と実感できるだけで、「明日も頑張ろう」と思えました。
②孤独にならず、学びの姿勢を持ち続ける
メンタル面でいえば、人とのつながりもとても大切です。半年でもいいので、どこかで“コミュニティ”を持つことをおすすめします。
周りの人と比べて落ち込むこともありますが、「羨ましい」とか「早く終わらせたい」という気持ちをモチベーションに変えることで、自分を奮い立たせるきっかけになります。
私は2回目の不合格のあと、BEXAの決起集会に参加し、自分の勉強法や成績の変遷、今後の戦略などをノートにまとめて持っていきました。
先生方に話を聞いたり、アドバイスをもらったりしたことが、日々の勉強に直結して役立ちました。自分からLINEで連絡を取ったり、話を聞きに行く“メンタリティ”が何より大事だったと思います。
この試験は長くて孤独な戦いになりがちですが、自分を客観的に見直す機会や、一歩外に出て人に相談する機会をうまく活用して、納得のいく受験生活を送ってもらえたらと思います。
使用教材一覧
| 科目 | 使用教材 | 補足情報・使い方 |
|---|---|---|
| 憲法 | 過去問のみ | 得意科目のため、演習書なしで伸ばす |
| 民法 | LawPractice民法、LawPractice民法攻略講義(葵千秋) | ロープラ中心に演習・理解。改正法対応の参考答案付き。 |
| 商法 | LawPractice商法、LawPractice商法攻略講義(望月楓太郎) | 苦手克服のため、「最低限これを覚える」指針が明確だった。 |
| 民事訴訟法 | LawPractice民訴、LawPractice民事訴訟法攻略講義(剛力大) 、過去問 | 「三段論法の上部分はこれでよい」と納得できた。 |
| 刑法 | 過去問、刑法事例演習教材 | 得意科目だったため過去問重視。理解優先。 |
| 刑事訴訟法 | エクササイズ刑訴法、リーガルクエスト刑訴、過去問、判例集、論証集 | 苦手強化のため集中学習。理解が曖昧な部分はリークエ・判例集で補完。 |
| 行政法 | 基礎演習行政法、実践演習行政法、憲法ガール、過去問 | テキスト読解と問題演習→復習時に憲法ガールで補完。 |
| 知的財産法(選択科目) | 過去問(17〜18年分)、趣旨規範ハンドブック | 5年分は答案作成/残りは構成のみ+出題趣旨・採点実感で確認。5月までに論証集の暗記を完了。 |
| 全科目共通 | 趣旨規範ハンドブック(論証集) | 暗記用教材として年内から直前期まで繰り返し使用。 |
・刑訴はリーガルクエストがいいんだ!とか、この科目は過去問だけでいいんだ!といった結果の部分に着目するのではなく、その選択をした理由、つまり自己分析の大切さ、司法試験の合格ラインとの距離の判断の大切さに気がついていただけたら嬉しいです。
・随所で「完了」したという表現をしていますが、ひとまずやる、一旦やったらそこから少しずつ精度を上げていくという趣旨です。一周目は30点の完成度でもいいので、何回かやるうちに合格点に届くような意識で勧めていってもらえたらと思います。勉強中は30点でも、試験の当日に合格ラインに乗れば、誰にもバレないので、完璧主義の方でも乗り越えられるはずです!
参考になれば幸いです。応援しています!
2025年7月25日
役に立った:7